第二章 険しい契約結婚⑥
琉河が谷木邸での監視任務を開始し、二日が経ち、三日が経った。
鬼人などという異名まで付くほど剣の腕が立つ琉河だが、何も妖と戦う任務ばかりを得意としているわけではない。
というより――正確には、琉河自身の目的に繋がる可能性が少しでもある任務にならば、それがどんな内容であっても全力で身を投じる覚悟をとうに決めていた。
言い換えれば、目的のためならばどんな手段も厭わない、ということである。
当然、見ず知らずの女、それも妖を自宅の敷地に集めて何かを企てようとしている疑いのある女と夫婦を偽装する程度のことは訳なかった。もし女が無罪だった場合には相手にとっては気の毒だとは思っていたが、それも桐野の抜かりのない手回しによりひとまずは円満に解決できた。
それにもし女のほうに妖との交流が本当になく、ただただこの土地だけが悪い気脈の通る場所だった、という結論に至ったとしても、原因は何にせよ妖がこの地に集まっていることは間違いないのだから、ここにしばらく留まることができるというのは琉河にとっては都合のいい話だった。
初対面の印象は――食えない女だな、だった。少し言葉を交わしただけで、頭の回転が速い人物であることはすぐにわかった。
琉河の目的の相手とこの女が繋がっている可能性は、今のところ五分だ。調査を進めないことにはまだ判断はできない。しかしその可能性が少しでもある以上、谷木比奈子という人物に最初から好印象など持てようはずもない。警戒心、ともすれば嫌悪感に近いものを抱いていることを相手に悟られないよう、淡々とした態度で接するほかなかった。
ほぼ初対面の女の独り住まいに身を置くという一見非常識な状況だが、琉河にとっては他の任務先に宿直するときと何ら変わらない状況である。つまり、檻の外から檻の中を観察するということ。対象には必要以上に干渉しない。対象がこちらを意識するあまり普段と違う行動を取りすぎては本末転倒である。だから自分はなるべく気配を消して、いないものとして振る舞う必要がある。対象の本当の行動を引き出すために――有り体に言えば、ぼろを出すよう誘導するために。
谷木比奈子という人物は、人生のあらゆる場面を一人で行動することに慣れていて、それを当然のこととして暮らしているようだった。そして他の一般的な二十代の女性に比べ、肝が据わっていて、どこか世の中を斜に見ているような雰囲気があった。琉河の存在は彼女にとっては異物そのものであるはずだし、未婚女性からすれば自分よりも腕力も権力も強い異性というのは恐怖の対象にもなり得るはずだが、彼女が琉河を恐れたり怖じ気づいたりしている気配は欠片も感じられなかった。
――対等だ、と、琉河は直感的にそう思った。
無論これは状況的にあり得ない話だ。自分は国家権力を持つ監視官で、相手は監視対象である。それでも谷木比奈子の態度は、この家を采配するのはあくまで自分であると言わんばかりに堂々としていた。法に触れるやましい部分をこんな近距離から探られようとしているのに、恥ずべき部分は自分には何一つないとでも言いたげな、それでいて肝心な腹の底は誰にもさらけ出さないような。
(……それは俺も同じか)
自分だってこの女に、この監視任務の本当の目的は伝えていない。それは下手に伝えることでこの女が隠し立てするのを防ぐ意図ではある。だから名目上は違法毒ガス密造の調査という体裁を取っている。
だが真の目的を相手に伝えることは、即ち琉河自身の弱味をさらけ出すことでもあった。
あるいは谷木比奈子のほうも、何か見られたくない弱味のようなものを奥底に抱えているのか。そんな埒もないことを思うほど、彼女は自分とあまりに対等であるように感じた。
だから、彼女が初日の夜、琉河に食事を出してくれたことは、琉河にとってはまったくもって予想外だった。監視任務での滞在期間中、彼女はこちらを空気のように――と言えば聞こえがよすぎるだろうか――あるいは家の中でやたら幅を取る邪魔で不便な大岩のような存在として扱うものだと思い込んでいたからだ。
調子が狂うな、と思った。
感情を無にして任務にあたっていたのに、一瞬、気が散じた。
そのまま四日が経ち、五日が経つ。同じ食卓に着いているのに別の空間にいるような異様な空気はそのままに、互いが互いの存在をないものとして過ごす。食事をともに取っている事実など端から存在しないかのように。
異様で、対等だ。
この五日、谷木比奈子は何ら怪しい行動を取ってはいない。妖を集めたり、妖と対話したりといった様子も一切ない。
家主の立ち会いのもと、琉河は家の中を幾度か見て回った。家主が寝静まってから琉河一人で改めて確認に行ったことも何度かある。
家の中も何というか、家主同様に少し変わっている。が、玄狼党をして『しょっちゅう妖が集まる気配がする』と言わしめたまさにその地点であるにしては普通だ、というのが琉河の正直な見解だった。
まず、主に二階の納戸として使用されている部屋の中に、神事か何かに使われるような大小の道具が雑多に押し込まれている。定期的に最低限の掃除はされている様子ではあるものの、家主がそれらの道具を積極的に愛用していないことは一目瞭然だった。
納戸の扉を開くなり問い質すような視線を向けてしまった琉河に、家主の女はややうんざりしたように肩を竦めてみせた。
「私の身辺は調査済みのはずよね。それなら私がこの家を親戚から譲り受けたの、ご存知でしょう? 私が住み始める前からこうだったのよ」
「それ以前の居住者がこの道具を使っていたかどうかは?」
「私が来るより前のことは何も存じませんわ。気味が悪いから売り払って生活費の足しにすることも考えたけど、何だかバチが当たりそうだったからやめたの」
この女は別段信心深そうには見えないが、同じく別段信心深くはない琉河も何となくそれには同意だったので頷いた。
とはいえこの家の中で最も怪しい部屋であるのも確かだったので、琉河は丸二日ほどかけてこの部屋にあるものを検めた。一見がらくたの山を搔き分けるように手に取って確認するうち、それらが琉河にとって非常に馴染み深いものだということに気付いた。
(これは神道……いや、古い陰陽道に関する道具か?)
裏中務の源流は陰陽寮だ。しかし名前も実態も時代とともに変遷し、今では陰陽師などと呼べる者は裏中務には存在しない。桐野以外に正しい知識を持つ人間がいるかも怪しいところだ。正直、琉河もよくは知らないし興味もない。この時代の妖と――琉河自身の目的と繋がらないのであれば知識を得る必要もないことだと思っている。
だから目の前のがらくたの山も、すべてが陰陽道の道具なのか、それとも神道のものが交ざっているのか、琉河には判別できない。しかし陰陽道に関する道具が山のように押し込まれた家というのはそれだけで珍しい。それが結果的にただの熱心な信者だという結論に至る可能性も高いにしろ、一旦は谷木家についてもっと詳しく調べてみる必要があるだろう。
この納戸以外にも変わっている点はあった。それは家中の至るところに気味の悪いお札のようなものが貼り付けてあることだ。お札には字なのか絵なのかわからないものが書かれているが、それが何となく目のように見えて何とも居心地の悪い不快感がある。子どもの頃、柱の木目が人の顔に見えて怖かった記憶に似ている。
これについても家主は顔を顰めてみせた。
「同じ説明を繰り返すことになって恐縮だけれど、私に説明できることは何もないわ」
しかしそれら以外の部分については、谷木家は至って普通の民家だった。事前の調査によればこの土地の所有者自体はずっと谷木家のままだが、上物は何度か建て替えられているらしい。今建っている家も、築年数は浅くはないが決して不自然なほど古すぎるということもない。とはいえあちこちにがたは来始めているようで、扉がばたんと閉まったり、家財道具が大きな音を立てて落っこちたりということはあるようだが、古い家ならばよくあることだ。人口の少ない田舎というわけでもないのに両隣の家からやや離れすぎている、という立地以外は何もおかしなところはない。
この立地についても、恐らく土地に集まっている気脈のせいだろうと説明がつく。悪い気が集まる場所は、人々は何となく寄りつかないものだ。街中や駅前など人が集まる場所なのに店がなぜかすぐ潰れたりする場所があるが、原因の多くはまさにこの気脈である。
良くない気脈には、良くないものが寄りつく。例えば、妖とか。
妖というのは実は、その姿は人間にも普通に見ることができる。裏中務や玄狼党に関わりのない一般人であればその記憶を夢か幻であったかのように書き替えられる、というだけだ。返して言えば、谷木比奈子が何らかの目的で妖をこの敷地に集めようとしているのだとしても、帝国中を網羅する神凪の呪によってその記憶は書き替えられるはずである。つまり企てはうまくはいかない。ただ、事実としてこの場所に集まる妖の気配を玄狼党の狼たちが警戒しているのは間違いないので、何らかの異変の兆候はこの家にも、そして谷木比奈子という人物にもあって然るべきだった。
琉河自身は妖と戦う際には、獰猛な獣と相対するときと同じ感覚である。つまり自分に向けられる敵意や殺意に向かって刀を振っていると言っていい。逆に言えばそうでないと妖の気配は察知できない。玄狼党の狼たちのように妖の匂いを嗅ぎ分けたりなどという特殊能力は、残念ながら琉河には備わっていなかった。いくら『鬼人』などという異名を付けられていても、その部分では自分は普通の人間と何ら変わらないと琉河は思っている。
そんな琉河が、この家の敷地に初めて入った瞬間、普段の任務にあたるときと限りなく近しい理由で自分の身体が緊張を帯びるのを感じた。つまり妖と相対するときか、それに近い負の気脈に足を踏み入れたときの、肌がひりつくような感覚だ。
それなのに谷木比奈子もこの家も、一向に尻尾を出さない。
明らかに何かがあって然るべき状況なのに何も起こらない。まるで他の多くの人々と同じようにごく普通の人間が、ごく普通に暮らしているふうなのである。
それが一層、何か言葉にするのが難しい類いの違和感となって、琉河に重くのし掛かっていた。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




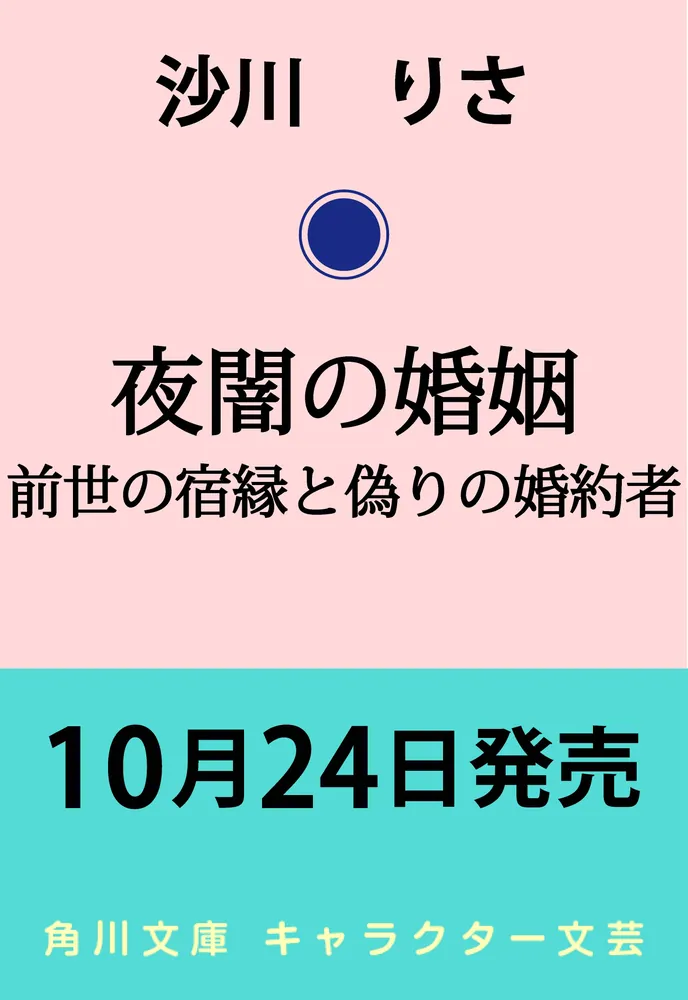
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます