第二章 険しい契約結婚⑤
気まずいまま夕食を終え、いざ入浴の時間が近づいてくると、現実逃避をしている場合ではなくなってきた。親しくもない人間と、しかも異性と同じ風呂に交代で入るというのが気まずいどころの騒ぎではないということに、ようやく実感を伴って気付いたのだ。
しかしこれは比奈子の杞憂に終わった。幸い目と鼻の先に銭湯があり、琉河はこの家に滞在中はそこに行くと言うのだ。それを聞いた比奈子は心から安堵しながらも、銭湯に行っている間に自分が毒ガスを密造していたらどうするのだろう、と監視対象らしからぬことが気になった。恐らくは比奈子の入浴中か、あるいは寝静まった後にでも行くつもりなのだろうとは思うが。
果たして想像通り、比奈子が入浴を終えて居間に戻ると、同じく入浴を終えてきたらしい琉河がそこで待機していた。待っていた、などという生やさしい態度ではなく、まさしく任務中の警保局職員らしい緊張感を保ったままの待機の姿勢だ。
が、髪はまだしっとりと濡れているし、あの目に眩しい白い制服ではなく落ち着いた色味の浴衣姿だし、首からは銭湯の手拭いが掛かっている。
出で立ちと本人の態度があまりに不釣り合いで、比奈子は戸惑うあまり彼をまじまじと見つめてしまった。
琉河もこちらを見ている。もっともこちらはまさしく監視している、という視線だ。
比奈子は不意に、自分も彼と似たような出で立ちであることを思い出した。湯上がりの油断しきった姿を、前世では敵だった男に見せてしまったことに、今さら後悔のような何だかよくわからない感情が湧いてくる。
(いないものとして、いないものとして……)
内心ぎくしゃくと、表向きにはなるべく滑らかそうに見える動きで、比奈子は普段通りに座布団に座り、手拭いで髪の水気を丁寧に取る。手拭いの裾で何となく顔を隠しながら、自分の浴衣が着崩れていないかをこっそり確認してしまう。何しろ普段は自分ひとりで、誰に取り繕う必要もなかったから。
(別にこの男に見られたところで、どうってことはないけれど)
それに第一、この男には前世で斬死体という生涯で最も無様な姿を見られているのだから今さらという気もする。
髪を乾かして白湯を飲み、絞った明かりの下で少しだけ本を読み、そして寝室に下がり布団に入る。そういう普段と何ら変わらない寝る前のお決まりの手順を、普段とまったく違ってしまった環境の中で粛々と進めた。
いないものとして、という言葉を呪文のように――あるいはお守りのように内心で唱え続け、おやすみなさいという挨拶も特に交わすことなく、比奈子は眠りに就いた。
隣の部屋からしばらく人の気配と物音がしていて、今夜は気になって眠れないかもしれないと思ったけれど、幸い自分はそこまで繊細なたちでもなかったらしい。ぐっすりとよく眠って、いつもと何ら変わらない、そしていつもと違いすぎる翌朝を迎えたのだった。
「――妹の仇」
憎しみをこめた言葉と、振り下ろされた刀の一撃とともに目覚める。
心臓も首の後ろもいつもと同じように冷たいし、夢の中でゆらゆらと揺れていた視界の名残で吐き気にも似た胸のむかつきがあるのもいつも通りだ。ひんやりと冷たい朝の空気の中、陽に照らされた古い梁の直線を確かめるのも。
だけど今朝は、布団に横たわったままそれを見上げる比奈子の心持ちがほんの少しだけ違っていた。
(……あの人、妹さんを何者かに殺されてるってことよね)
今までそのことについて深く考えたことはなかった。何せ相手は覚えのない罪で自分を殺した憎き敵だ。状況から察するに、恐らくは妹を妖に殺されていて、比奈子のことをその妖を配下として侍らせている親玉だとでも思っていたのだろう。あるいは比奈子が妖に命じて殺させたとすら考えていたのかもしれない。そうでなければあんなこの世のすべての憎しみを煮詰めたような視線で突き刺される謂れがない。
起き上がり、枕もとに置いていた肩掛けを羽織る。今朝は昨日よりも少しだけ温かい。こうして温かくなったり寒さが戻ったりしながら、本格的な春へと向かっていくのだろう。
そう遠くないうちに咲くのであろう桜を、彼の妹が見ることは叶うのだろうか。
(それとも、今生でももう既に……?)
前世で彼と出会ったのは今よりも一年先のことだ。妹に関して今の彼がどんな状況にあるのか、勿論比奈子にはわからない。ただひとつはっきりしているのは、今の彼は比奈子を妹の仇だと見なしてはいないであろうということだ。今後の比奈子の身の振り方ひとつで――万が一妖を匿っていた事実がばれてしまった場合、どう判じられるかはわからないにしろ。
(あの男がここにいる間は、裏庭側の襖は不用意に開けないほうがよさそうね)
自分の性分として、梅の木の下の妖を、見つけたら助けたくなってしまう。ならば最初から目に入らないようにするに限る。
顔を洗うために寝室から出ようとして、ふと鏡台に並んだ化粧品を見やった。
(まあ、必要ないわよね)
どうせ昨日も素顔のままだったのだし今さらだ。他人の前で最低限の身だしなみを整えるにしても、単なる他人ならばいざ知らず、そんな気を遣わねばならない相手でもない。
寝室の襖を開くと、隣室で機を窺っていたのだろう、ほぼ同時に琉河が部屋から出てきた。既に身支度を調えた姿だが、本人の申告通り、今日は白い制服ではなく、落ち着いた色味の洋風の軽装といった出で立ちである。
広くはない廊下で真正面から鉢合った格好だが、客でもなければ友人でもなし、普通に朝の挨拶をするのも何だか妙な気がする。
(……いないものとして)
昨日から何度も繰り返したその言葉をもう一度頭の中に刻み直し、それでも一応軽い目礼だけはして、比奈子は寝室の襖を閉めようとした。
と――そのとき、ばたん、と背後から音がした。
背筋がひやりとする。何の音なのかは勿論わかっている。
振り返ると、あの額装された絵が畳にうつ伏せに倒れている。裏庭に面した襖は開けていない。
昨日はこの家にとって初めての闖入者であるこの男を家のほうも警戒していたのか、まるでじっと息を殺して様子を窺っているかのように、怪奇現象は鳴りを潜めていたのに。
琉河も倒れた絵を見ている。比奈子は何でもないふうを装いつつ、屈み込んで絵を壁に立てかけた。
「嫌ねぇ、古い家だから隙間風がひどくって」
そんな独り言を言いながら、我ながら大根芝居だと顔を覆いたくなった。絵から手を放す直前、思わず爪を立てるようにして額を強く握り締める。
(あんたたち、わかってるわよね? 頼むから空気を読んでよ)
念を押してから立ち上がり、今度こそ襖を閉める。廊下を歩き始めた比奈子の後を、昨日と同様、琉河は一定の距離を保ちながらついてくる。
それはそのままこの男との心の距離のようにも思えた。
この男に妹のことを訊いてみることはこの先一生ないのだろうな、と比奈子は思う。他ならない比奈子自身の命運にも深く関わってくることなので気になりはするけれど、自分がこの男とそんな込み入った雑談に興じている姿など、まったく想像がつかなかった。
この男との距離なんて、縮めようとも、縮めたいとも思わない。この一定の距離を保ち続けたまま、無事離縁となり、彼がこの家を去る日が早急に来てくれることを願うのみだ。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




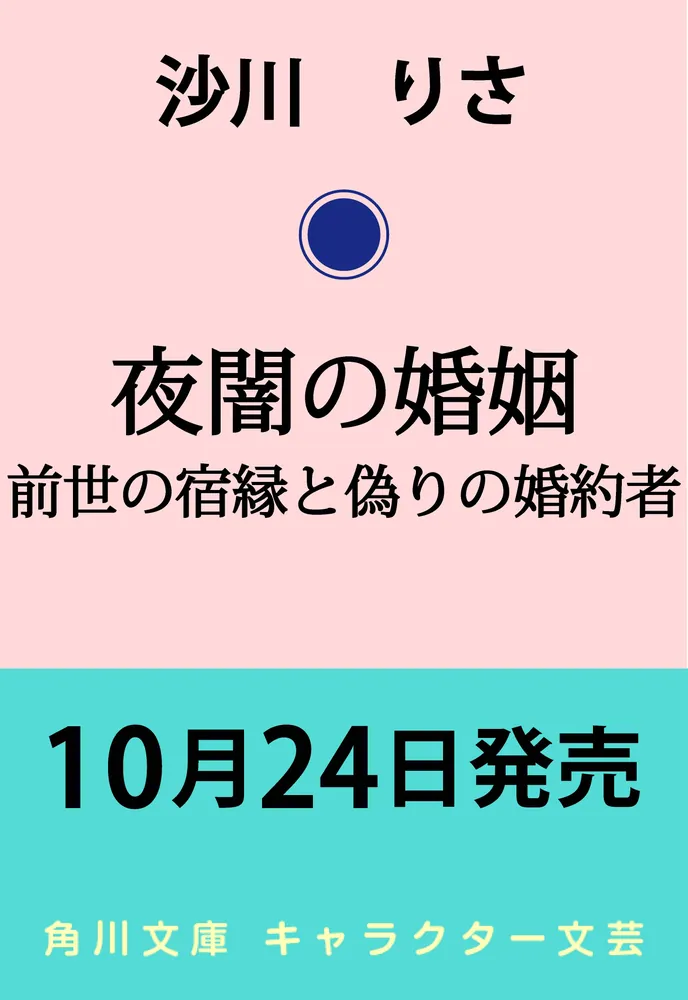
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます