第二章 険しい契約結婚④
結局、比奈子は夕食を同居人の分も作ることにした。何が自分にとって居心地悪いのか、どうすればそれが少しでもましになるのかを熟考した結果だ。
相手をもてなしたいなどという高尚な目的からではない。ただ自分だけがちゃんとした食事をしていて、自分の視界に入る場所にそうではない人間がいる、そのせいでこちらまで食事がおいしくない、という状況を何度も繰り返すぐらいなら、そうではない状況を自分で作ったほうがいくらかましだと思っただけのことだ。
比奈子は生まれつきの性分として、目に入り手の届く範囲のものを放ってはおけない。敷地内に迷い込んでくる妖を放っておけないのと行動原理としてはまったく同じだ。これは性格なのだからもう仕方がない。
生まれて初めて二人分の食事を用意しながら、比奈子は何だか妙な感覚に襲われた。
これまでにも多めに作り置きをすることは勿論あったが、それを自分以外の誰かが食べるというのはものすごく不思議な感覚だった。こんなもの他所様に食べさせて本当に大丈夫かしら、とそわそわしながら肉じゃがや切り干し大根の煮物を二人分盛り付け、琉河の前に差し出す。
「……お口に合うといいのだけれど」
前世での敵に向かって何を言っているのかしら私は、と半ば馬鹿馬鹿しく思いながらも、この言葉も間違いなく自分の本心だった。
卓袱台の向こうの壁際で相も変わらず手帳に何か書き付けながらこちらを見ていた琉河は、はっきりと驚きの表情を浮かべて目を瞬かせた。
(何よ。そんな顔しなくてもいいじゃないの)
相手だってまさかこちらが自分の分まで食事を作っているとは思いもよらなかったのだろう。琉河が口を開きかけたので、比奈子は先回りして言い放つ。
「一人分も二人分も大差ないからついでよ、ついで。あなたの分の材料費はもちろん頂きますから」
「……すまない。手間を掛けた」
「お気になさらないで。自分と違う食事を同じ空間でされるほうが迷惑ってだけ」
あえて棘のある言い方をしたのだが、琉河は頷いて続けた。
「なら、明日からは交代制でどうだ」
本当にただ仕事で宿直している人間が同僚に提案するような言い方だ。比奈子は素直に意表を突かれてしまい、そのせいで反応が一呼吸遅れた。眉を顰めて首を横に振る。
「お台所は触られたくないわ」
それは正直な言葉だった。料理が特別好きなわけでも何でもないが、化粧品を勝手に触られたくないという感覚に似ている。恐らくは食材や調味料などの消耗品は、本や化粧品などと同様、比奈子自身が自分の目で見て自分の足で買い集めたものだからだろう。その証拠に、この家にもともとあったものはいくら勝手に触られようが何とも思わない。言ってしまえば壊されたとてどうでもいいとすら思う。
日常に突如入り込んできた異物であるこの男に今、はっきりと境界線を示したのだと自分で気付き、比奈子は目の前の男を窺い見た。
琉河のほうも恐らく比奈子の真意には気付いているだろう。そして恐らくは気付いた上で、何事もなさそうな顔で淡々と答えてきた。
「わかった。捜査に直接関係のない部分であれば、こちらは家主の意向に従う」
「触られたくないとは言ったけど、もちろん捜査は気の済むまでしていただいて結構よ。毒ガスの材料を味醂やお塩の間に紛れ込ませているかもしれないものね、もし私が本当に毒ガス密造の犯人なら」
しれっとそう告げつつ、比奈子はもう一度琉河に卓袱台の上の料理を示して食べるよう促した。
琉河は比奈子の顔を確認するようにちらりと見た。こちらがどの程度嘘を吐いているのかを見極めようとしているように見える。比奈子はひとつ嘆息した。
「……お料理してる間一部始終を後ろに突っ立って見てたんでしょ。毒なんて入れちゃいないわよ。同じものを私だって食べてるのよ、今」
「ああ――すまない。別にそこを疑ったわけではなかったんだ。申し訳ない」
その言いように比奈子はやや調子を崩しそうになる。
「そう何度も謝られると余計にやりづらいから、いただきますとだけ言ってもらえると助かるんだけど」
「……わかった。いただきます」
「どうぞ」
しかし琉河は目礼したきり、やはり食事には手をつけない。比奈子が一人で食べる様子を黙々と見つめている。
これはもう、耐えられないほど居心地が悪い。
「……あのね」
「わかっている。後でちゃんといただく」
「私が寝た後に?」
琉河は頷く。比奈子は深く嘆息した。
「手間を掛けたことをすまないと思うのなら、せっかく作ったご飯を作り手の前であったかいうちに食べないことにもすまないと思ってくれる?」
すると琉河は目を瞬かせた。そんなことを言われるとは思いもよらなかったという顔をしている。
じっとりとした目を向ける比奈子の前で、琉河はやがて観念したように手帳を懐にしまった。そして代わりに箸を取る。
黙々と食べ進めるその姿を、比奈子は何となく固唾を呑んで見守ってしまう。
が、うんでもなければすんでもない。旨いとも不味いとも顔に出さない。いないものとして、という言葉を何度も頭に浮かべながら、比奈子も自分の食事に集中することにする。
よく味の染みた牛肉を咀嚼しながら、はるか昔――前世でまだ勤めに出ていた頃、同僚との雑談中に、肉じゃがの肉がこちらでは豚が主流であると聞いて驚いたことを思い出した。味付け自体も比奈子好みの関西風の甘塩っぱいものだ。
比奈子は思わず向かいに座る男の顔をちらりと盗み見る。箸は進んでいるようだから問題はないはずだと思いたいが。
(……別に好みの味付けじゃなくたって私の知ったことじゃないわ。ここは私の家で、この家の主は私なんだから。相手が私に合わせるのが筋ってものよ)
もし交代制の料理当番の案を受け入れていたら、比奈子の好みではない関東風の味付けの料理を食べることになっていたことだろう。今はもうすっかり慣れたが、帝都に越してきたばかりの頃は外食するにも食べ慣れない味に少し苦労したことを思い出す。
交代制を突っぱねておいてよかった、と安堵する反面、ほんの少しだけ残念にも思った。二度目の生を歩む今の自分になら、関東風の味付けを昔よりは興味深く食べられたかも、と。
(私ったら、おかしなことを考えてる)
普段なら考えもしないようなことを、さっきからのべつ幕なしに考えてしまっている。
きっとこれも全部、住み慣れた日常の風景の中に、あり得ない非日常の異物が入り込んでしまったせいだ。
目の前の男の皿がみるみる空になっていくのをぼんやり眺めながら、お風呂はどうするんだろう、と比奈子は半ば他人事かのように現実逃避気味に思った。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




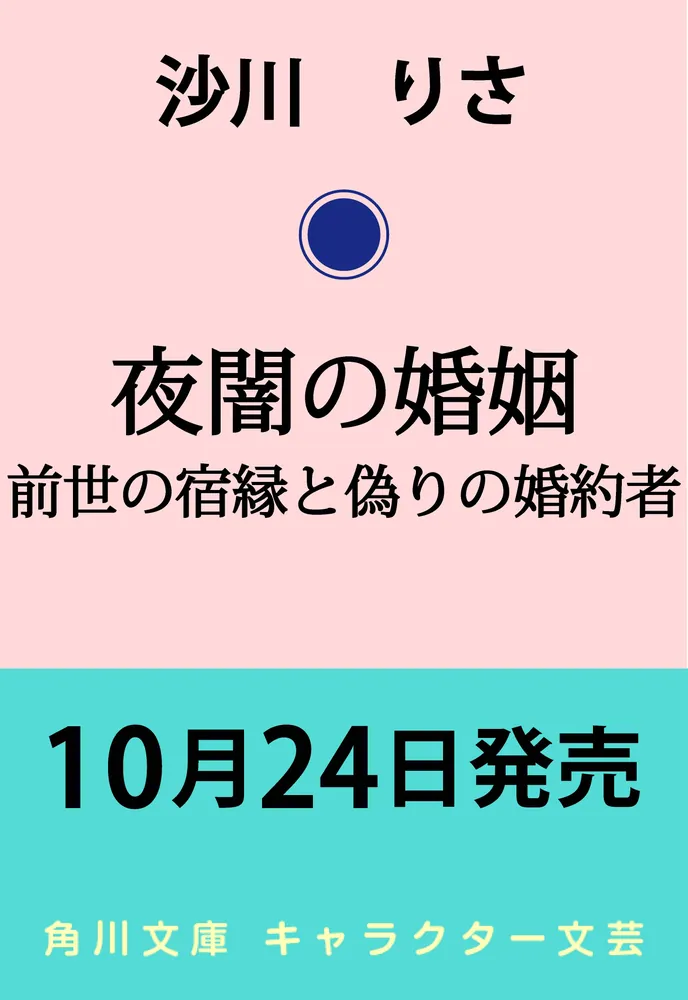
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます