第一章 再びの生⑦
「
部屋を出た琉河は狭い廊下を抜け、その先にある小部屋の前に立ってそう声を掛けた。
重役の個室と呼ぶにはあまりに簡素すぎる作りだ。何しろ畳敷きの小上がりの八畳間に卓袱台と座布団、茶を淹れるための細々とした道具、それに小さな書類棚が置かれているのみである。桐野本人も本格的な調べ物などをする際には事務所のほうにやってくるので、ここは実質桐野の個人的な休憩室のようなものだった。
中から返答があったので扉を開くと、部屋の主であるいかにも摑みどころがなく飄々とした風体の和装の老人が、細身の身体で胡坐を組んで茶を啜り、濃い色の煎餅をぼりぼりと食べていた。琉河の顔を見るや、おお、と相好を崩す。
「掛井くん、戻ったか。煎餅食うかの?」
「いえ、結構です」
「なんじゃ、旨いのに。後で悔しがっても知らんぞ」
こちらに見せびらかすように「ほれほれ、お前も食わんか」と煎餅を囓る老人の姿に、知らず強ばっていた背筋が解けていく。緊張感がなさすぎて気が抜けたとも言う。
琉河は差し出される煎餅を丁寧に固辞しつつ、持参した書類を桐野に差し出した。
真っ白な眉毛がぴくりと動き、普段はその眉毛にほぼ隠れている目がきらりと光る。
「例の『とある地点にしょっちゅう妖が集まる気配がする』アレじゃな?」
桐野は卓袱台にぞんざいに置かれていた眼鏡を掛け、書類を覗き込む。琉河は頷いた。
「以前より玄狼党から情報が共有されていた件です。中野から阿佐ヶ谷にかけてのある地点からそういう気配がする、と」
「しばらく様子見扱いになっておったな。まあ、玄狼党の狼たちの特性と任務内容を考えれば仕方のないことではあるがの」
玄狼党の狼たちは、妖たちが放つ殺気を察知して討伐に向かうという。件の地点からは妖が集まる気配がたびたびしており、一瞬強い殺気を放つために狼たちの警戒網に引っかかっていたのだが、その強い殺気というのが本当に文字通り一瞬で消えてしまうため、今すぐ出動しなければならないほどの緊急性はないと判断され続けていたのだそうだ。そのため長いこと様子見扱いになっていたという案件である。
要は他のことで手いっぱいなので後回しになっていた、ということなのだが、そうは言っても玄狼党の中でも「そろそろ何か手を打ったほうがいいのではないか」と懸念を示す者が出てきたらしい。「何者かが妖を一ヶ所に集めて良からぬことを企てようとしているのだとしたら、こちらの対応が後手後手であるのをいいことに事態はもう進んでしまっているかもしれない。今このときも既に手遅れの可能性もある」と。
その言い分は琉河にもよくわかるし全面的に同意見だ。焦り始めるのが遅いくらいである。
しかし玄狼党が動き出すのが遅かった理由も理解できる。基本的に彼らは、彼らにしかできない任務――つまり脅威となり得る妖の討伐任務で忙しすぎるのだ。手が空いているときも決して暇なわけではない。いつどこで何が起きても急行できるよう待機している状態なのである。つまり「目を光らせておいたほうがいいのはいいが、その結果特に何もないかもしれない」という案件を注視し続けることに人員を割けないのだ。
そして裏中務の任務の多くは、実はそういった案件が占めている。
「つまりその地点の監視を正式に依頼してきたというわけじゃな。幹部の中でも頭領の次に力を持つ若造を寄越してまで。なるほど、なるほどなぁ」
桐野は仙人のように伸びた白い顎髭を何度も撫でた。
――この桐野という老人は、のらりくらりとしているように見えて、先を見る目が驚くほど優れている。今はまだ大した事件ではないが後々重大なことに発展してしまう、というような案件を嗅ぎ分ける能力に異様に長けているのだ。裏中務はそういった桐野の手腕によって何度も危機的状況を乗り越えてきた。そのため裏中務内では「桐野さんって実は人間じゃなくてぬらりひょんか何かなんじゃ……」という噂すらまことしやかに流れている。
今この瞬間まで、この監視任務は部下たちの誰かに振ろうと琉河は考えていた。しかし桐野の様子を見てその認識を改める。
自然、背筋が伸びた。桐野の白い眉が上がり、その双眸が琉河を見る。
「この特殊任務を任せられる者は、裏中務の中でも一番の実力者であり仕事に忠実なお前さんしかおらん。掛井琉河――お前さんを実地調査官に任命する」
琉河は頷き、それを拝命した。
どんな任務であろうと、琉河にとっては他の任務と同じように忠実にこなすだけだ。
(今度こそ何らかの手掛かりを得られるかもしれない)
そう頭の片隅に浮かべながら、その身体は冷静に、酷薄に軍刀を振るうだけ。
自分が任命されたからには、ただの監視任務では当然ないのだろう。恐らくは部下たちの手には負えないような危険を伴う可能性がある。
(望むところだ。そうであってこそ、俺は俺の『仇』に近づける)
だが、桐野がなぜ特殊任務などという耳慣れない言葉を使ったのか――その理由を、琉河は間もなく知ることになる。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




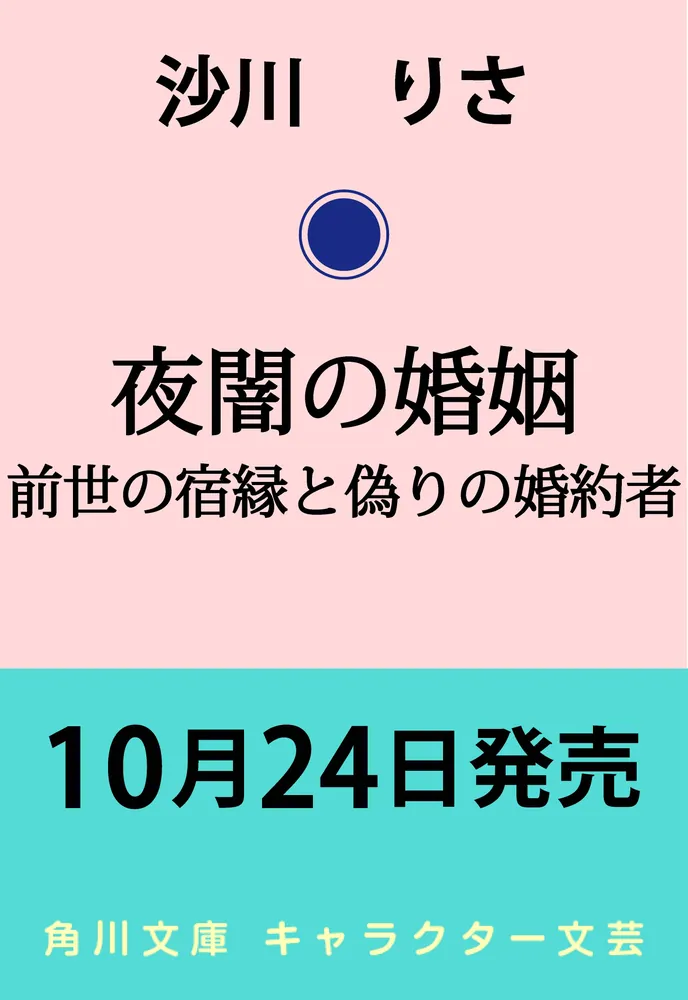
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます