第一章 再びの生⑥
端正な顔立ちのその青年――掛井はいつものきりっと厳しい目つきで大河内と若林に目礼を返した。この目で見られると背筋が伸びるんだよな、と若林は思い、その思考通りに己の姿勢を正す。
「留守中変わったことは?」
「いえ、何も」
「そうか。ならいい」
掛井が腰の剣帯から軍刀を外すと、大河内が流れるような動きでそれを受け取り、壁の刀掛けに恭しく置く。
小姓さながらの大河内に、同じく今しがた帰還したもう一人の青年が苦笑した。掛井よりもやや線は細いが長身で、やはり同じく隙のない雰囲気の男だ。
「君はいつだって掛井
「
大河内がその軽口には一切反応を示さないので、若林が代わりに声を掛ける。青柳は自分で軍刀を刀掛けに置きながら頷き返した。
掛井のために茶を淹れに行った大河内のことはひとまず無視しておいて、若林は机の上の資料を取り上げた。掛井と青柳が先ほどまで当たっていた任務に関するものだ。
「今日は例の件について玄狼党の幹部と会合だったんですよね。どうでした?」
それに答えたのは青柳だ。
「先方が手配してくれた店の昼食は大層美味かったよ」
「じゃ、今度俺も連れてってくださいね。ごちそうさまです」
「君には冗談が通じないな、若林」
青柳は肩を竦めてみせ、傍らの掛井を親指で指し示した。
「ちょっと時間が空いたから、奴が向こうの幹部と手合わせしたんだが、その後しきりに玄狼党に入る気はないかと誘われていたよ」
掛井は少し顔を顰めて青柳を見る。
「あの調子のいい狼がそう言い出すのは今日に限ったことじゃない。挨拶代わりみたいなものだ」
「挨拶代わりに帝国随一の、しかも妖ばかりの精鋭戦闘集団に勧誘されるのがもうさぁ」
「それに俺はあの男が苦手だ。奴が頭領の右腕を務める組織なんざ冗談じゃない」
「まあ琉河と相性悪そうな感じではあるよな。向こうは思いっ切りお前のこと気に入ってるみたいだけど。いつかうちの頭領と手合わせしてみてほしい、とまで言われてただろ、さっき」
それを聞いた若林は思わず誇らしさに胸を張ってしまった。大河内じゃあるまいし、と我ながら思いはするが、大河内ほど熱心でなくても裏中務に所属する男なら正直、掛井に憧れない者などいない。異名は伊達ではないのである。
掛井琉河は恐らく、人間の中では帝国中で一番の剣士だ。帝都の平和を脅かす魑魅魍魎どもに、非情なほど冷徹に軍刀を振るい、表情ひとつ変えず淡々と任務をこなすその姿は『鬼人』そのものだった。裏中務の隊士にのみ与えられた、妖に対抗するための呪が施された特殊な軍刀は、そもそも並の人間には扱えない。その刀を掛井はまるで自分の腕であるかのように、あるいは牙や鉤爪であるかのように自由自在に操るのである。
ちなみに玄狼党の連中が使用する対妖用の軍刀は、裏中務の軍刀とは違い、狼の妖の爪や牙を混ぜて打たれたより特別なものであるらしい。狼の、と言われれば納得感はあるが、実際にはあの人間と何ら変わらない容姿をした――確かに誰も彼も人間離れした美貌を持ってはいるが――連中の爪やら歯やらなのかと思うと、何とも言い難い気持ちになる。
ともあれ妖の討伐は基本的には玄狼党の役割で、裏中務の任務はあくまで人間たちや街を守ることだ。いくら呪の施された特殊な武器を使用しているといっても、妖というのは本来、人間の手に負えるような存在ではないからである。そのため戦闘よりも救助活動のほうが割合としては遙かに多いのだが、掛井に限っては例外だった。何しろ人間でありながら、高位の妖の精鋭集団である連中と対等に渡り合えてしまうのだから。
掛井は持ち帰ってきた鞄から会合の資料が入った書類入れを取り出すと、それを示しながら言った。
「報告に行ってくる。長くなるかもしれないから、その間に何かあれば青柳の指示に従ってくれ」
「わかりました」
若林は神妙に頷く。裏中務の任務は基本的に玄狼党の動きと連動しているが、彼らが動けないときや人間が動いたほうがいいときなどには緊急の出動命令が下ることもある。若林ら隊士たちの動きを取りまとめるのは隊長である掛井の役割で、掛井がよく指示権を預けるのは、彼の同期である青柳だ。副隊長という役職は存在しないものの、実質似たようなものである。
「荷が重いなぁ」
さして問題でもなさそうな声音で青柳が肩を竦めた。彼はこう見えて、恐らくこの裏中務では掛井に次ぐ使い手だ。
掛井は部屋を出て、同じ地下にある別室へ向かっていく。青柳も自分の席に着いて書類整理に取りかかっている。
若林はとりあえず、気の進まない机仕事に戻ることにした。
淹れたての茶が載った盆を携えて戻ってきた大河内が掛井を探してきょろきょろしているが、まあ大した問題ではないだろう。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




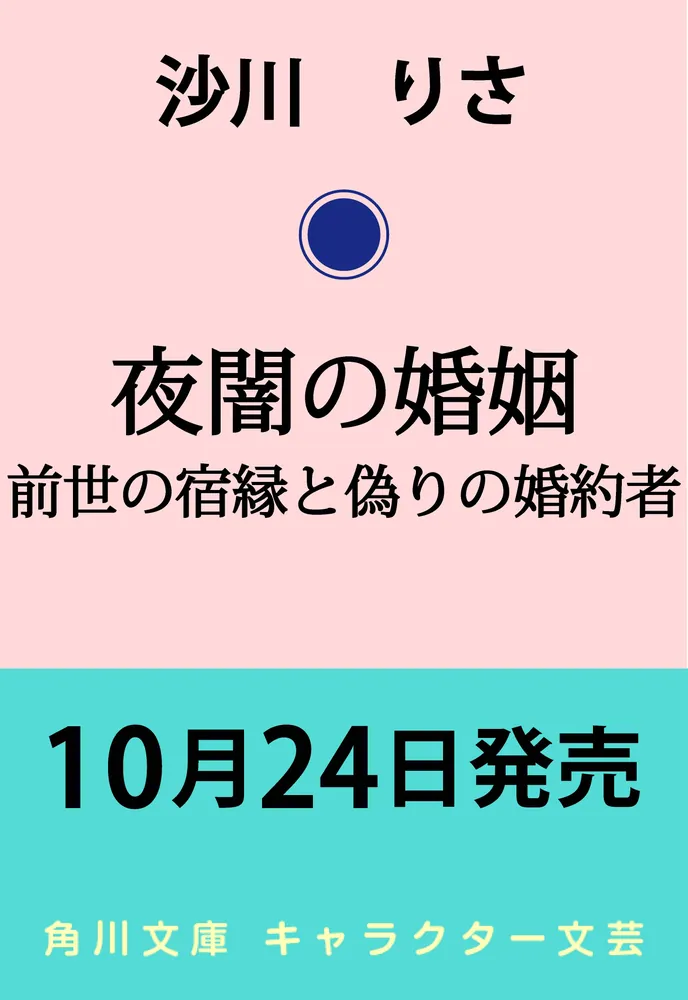
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます