第一章 再びの生⑤
2
皇居日比谷濠に面した日比谷公園は、この帝国で初めての近代的洋風公園である。
鶴を模した噴水に代表される美しい景観は、人々の憩いの場として親しまれている。路面電車の走る銀座の目抜き通りからもさほど遠くはなく、華やかに着飾った紳士淑女たちは、柳の並木に彩られた西洋の香り漂う街並みを歩き、買い物に珈琲にと楽しんだ後、ある者は白い装飾煉瓦も豪華な劇場へ、そしてある者はこの日比谷公園へと足を運ぶのだ。
江戸の世においては、この辺りは入江だった。日比谷濠はその名残だ。そのためこの辺りは地盤が緩く、大きな建物を建設しての有効活用は難しかったため、様々な経緯を経て公園が造られることになった。
――ということに、表向きはなっている。
実際には、日比谷入江の遙か地中深くには、塗り固めたように堅牢な大穴がもともと空いていた。それは数百年前には、土蜘蛛という巨大な蜘蛛の妖の群れがかつて棲んでいた巣穴の名残だった。その地下空間を、いつしか武器庫として利用する人間が現われた。この帝都を陰から守っている組織――裏中務だ。
現在、裏中務の隊士たちが詰める事務所は日比谷公園の中にある。さも公園関係の事務所のような顔をして建っている建物のうちのひとつがそうだ。否、正確には、実際に公園関係の事務所であることに間違いはない。その地下が裏中務の事務所であるというだけで。
かつて武器庫だった大穴は現在、裏中務の地下事務所から直通で繋がっており、武器庫ならぬ書庫兼、隊士たちの詰所として使用されている。
明るく華やかな日比谷の街を歩く人たちの誰も、地下にこんな陰気で広大な空間が広がっているなんて思いもよらないだろうな――と、その詰所の中で
とはいえ、陰気な、というのは言葉の綾だ。照明器具の数も光量も十分に足りているので薄暗くはないし、ここに詰める者たちは皆眩しいほどに真っ白な制服を着用しているので、地上で照明もろくにない部屋に閉じこもるよりはましだとすら思える。
では何が陰気なのかというと、この巨大な地下室の壁という壁をみっちり埋め尽くしている膨大な書物や書類の数々だった。
若林はもともと己の体力を恃んで生きている質なので、本やら何やらにはとんと縁がない。文字の羅列を見ているだけで眠くなってしまう。それでも一応はここが自分の職場であり詰所であるからには、上から命じられない限りはここで机仕事をするしかないのだった。
紙もので埋め尽くされた壁に四方を囲まれながら、沢山の机と椅子もまた目がちかちかするほどみっちりと並んでいる。
そしてもうひとつここが陰気な理由が――今の若林にとってはこれが一番の問題だが――、自分と同じ部署内で席も近い、折り合いの悪い同僚が、猫背をさらに丸くしながら一心不乱に鉛筆を動かしているからだ。いつも睨んでいるような目つきでぼそぼそとしゃべるし、事務仕事が一切苦にならない質なのか今のように詰所の番を命じられている間も手を止めないしで、若林にとっては何だか気味の悪い相手なのだった。
「もうすぐ
完全に手持ち無沙汰で時計を示しながらそう言ってみる。天気の話を振るのと大差ない。すると大河内は手も止めず、ちらりとも視線もこちらに寄越さず答えた。
「わかっているならそのでかい図体で無駄に幅を取ってないで隊長のために少しでも働きたまえ」
一息でそう言われて、若林は思わず溜息を吐いた。
大河内とは同じ時期からここで務め始めた同期と言っても差し支えない存在だが、この男に対して同期らしい絆を感じたことなどただの一度もない。
(確かに隊長に心酔する気持ちはわかるけどな。俺だって尊敬してるし)
――かつてこの国には、中務省という天皇を補佐する官庁が存在した。もう途方もないほど遙か昔の話だ。
中務省には不思議な力を持つ人間たちが所属していて、その力でもって裏からこの国を鎮護してきたという。その中務省が時代の変遷に従って少しずつ形を変え、名を換え、消滅の危機に何度も瀕しながらもこの時代にまで細々と残ってきたまさにその姿こそがここ、裏中務である。
この帝国には人や獣と同じように、妖が存在している。
それらの魑魅魍魎どもと平和的に共存するための組織の本部が、この帝都には二つ存在している。
一つは内務省警保局
そして今一つの組織が、この裏中務だ。
玄狼党の隊士たちは対妖戦に特化した特殊な刀を持ち、人間に害なす妖たちと戦い討伐する。そうすることで人間たちの社会を守る一方で、人間を害さない妖たちの暮らしを同時に守っている。
翻って裏中務は、若林が知る限りは人間の隊士たちによって編成されている。若林本人も含めてだ。
その理由は、人間社会では妖は実在しないことになっていることにある。
この帝国には、件の中務省陰陽寮に所属していたとある術者――神凪の末裔によって、国中を覆う大きな結界が張り巡らされている。その結界の中にいる人間は、もし妖と行き会うことがあっても、その出来事自体を夢や幻だと思い、実在するなどとは露ほども思わなくなるそうだ。人間と妖が末永く共存するために必要な、双方を守るための呪であるらしい。
かく言う若林も、恵まれた体躯を活かした柔術の腕を買われて裏中務に入るまでは、妖が実在するなどとは思いもしなかった。すべては娯楽や教訓のための作り話だと思っていたのだ。
裏中務や玄狼党に関わる人間は、組織に正式に加わる前の試験において、妖に関するいかなる情報も外部には漏らさないという誓いを交わす。恣意的に誓いを破った者には相応の罰が下る。罰の具体的な内容は黙されているが、今までにその罰を受けたという者の記録が残っていないことからも、その罰がいかに厳格に下されてきたかということが窺える。つまりは記録も残さず消されるということだ。
とはいえ昔の時分ならいざ知らず、今の時代に妖だ何だと往来で喚き立てたところで、頭のおかしい奴の与太話だと片付けられて終わるだけのような気もするが。
そんな誓約を交わしてまで裏中務が人間で組織されているのは、人間の中にも妖が実在することを知る者がいたほうがいいと先人が判断したからであるらしい。人間と妖の両方を守ることが目的で、尚且つ玄狼党が妖で組織されているのなら、もう片方の組織である裏中務に人間が選ばれるのも道理というものである。
ともあれそんな特殊極まる職場なわけだが、若林がここで働き始めたのには理由がある。というより、裏中務で現在働いている人間出自の隊士たちのほとんどが若林と似たような境遇だと言えるだろう。
若林は以前、親友と一緒にいるところを獰猛な妖に襲撃された。滅多に人里には降りてこない妖だというから不運というほかなかった。幸いにも若林自身は軽傷で済んだが、親友はその襲撃により片足を失ってしまった。
そのときその妖を討伐するために駆けつけたのが玄狼党の狼たちで、片足を失った親友を手当てし、呆然と立ち尽くす若林ともども保護してくれたのが裏中務の人間たちだった。黒い軍服に身を包んで妖と戦う玄狼党に対し、白い軍服を纏った裏中務は戦いによって傷ついた人々を救助したり、家や通りの損壊を直したりといったものが主だ。時には裏中務の隊員が妖と戦うこともあるが――玄狼党よりも裏中務が現場で先に妖と行き会ったときや、滅多にないが裏中務が玄狼党に「自分たちが討伐するから手出し無用」と事前に通告していたときなど――、基本的にはその任務は人間に一層寄り添ったものである。
裏中務は片足とともにそれまでの職を失ってしまった親友に、座ったままでもできる別の仕事まで斡旋してくれた。若林はそんな手厚い世話に恩義を感じたのと、親友のような不幸な人間を一人でも多く救うために、裏中務の隊士に志願したというわけだ。
もし可能ならば玄狼党に入りたかったほどだったが、何しろ玄狼党の隊士たちは文字通り人間離れした強靱な体躯と戦闘力を誇っている。柔術が強いだけのただの人間である自分には、あそこでは三日とやっていけないだろうと思う。
(俺なんかにゃ無理な世界だな。多分、通用するのはこの裏中務の中じゃ――『鬼人』ぐらいだ)
そのとき詰所の扉が外から開かれ、二人の男が帰還した。
姿を見るや、大河内がさっと素早く席を立つ。壁の掛け時計を見て、そして四十五度ぴったりに頭を下げる。
「時間通りのお戻り、お帰りなさいませ。任務お疲れさまでした」
つくづく気味の悪い男だな、と若林はそんな大河内の様子に顔を顰めながらも、一際堂々たる立姿をした白い軍服姿のその青年に一礼する。
「お疲れさまです、掛井隊長」
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




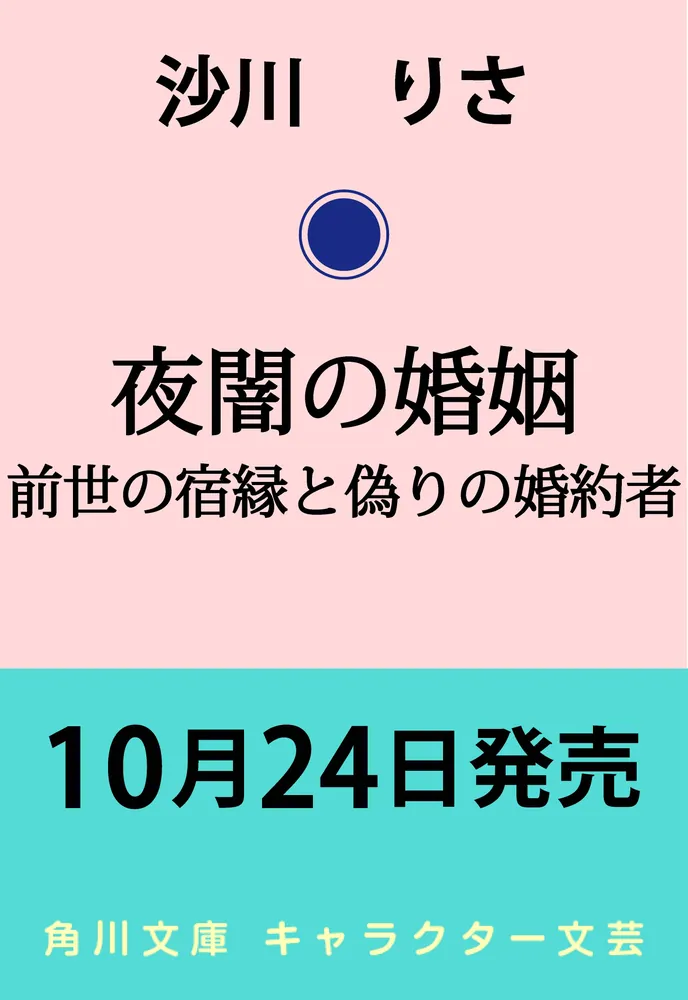
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます