第一章 再びの生④
うっかりしていて朝食の材料がないことに朝気付いたとしても、その足で自由気ままに出来合いのものを買い出しに出られるのが一人住まいの利点のひとつだ。料理は別に嫌いではないが、今朝のように面倒なときは惣菜屋で適当に買って済ませてしまうこともよくある。
買い込んだ惣菜を包んだ風呂敷包みと、途中の古書店で気まぐれに購入した一冊の本を手に帰路に就く。家からほとんど出ない生活を謳歌している比奈子にとって、本は時間を有意義に過ごすための貴重な娯楽だった。英国の切り裂き何某をはじめとした西洋の事件や文化などを知ったのもそういった書物からだ。
と、通りの向こうから隣家の住人である年配夫婦がやってくるのが見えた。隣家といっても比奈子の家は一軒だけぽつんと離れたところに建っているし、近隣住民が寄りつくような家でもないしで、その住人と話したことはほとんどないのだが。
普通の近所付き合いならばここで「いいお日和ですね。どちらへお出かけですか?」などと挨拶代わりの雑談のひとつも交わすのだろう。
(というか、前世なら私もそうしていたけどね)
比奈子はさっき買い求めたばかりの本を徐ろに開いた。そして頁に目を落とし、脇目も振らずにそのまま歩き続ける。
視界の端で隣人夫婦が、お隣の、と目配せしているのが見えた。妻のほうが一瞬比奈子に話しかけようか迷うような素振りを見せたが、比奈子が気付いていないと思ったのだろう、声を掛けることなくそのまますれ違った。
後ろからひそひそと話し合う声が聞こえてくる。
「ほらね、言った通りでしょう。ご近所付き合いも結婚もしないで、一人で家に籠もって本ばかり読んでるって。若くて美人なのにろくにお洒落もせずにもったいない」
「仲人でもしてやったほうがいいのかなぁ。近所の誼として」
「よしましょうよ、あんな変わり者と関わり合いになるのは」
「何でも首を突っ込みたがるお前にしちゃ珍しいじゃないか」
「だってあの人、ほんの娘時分から一人住まいなのよ、あのぽつんとした家で。お裾分けを持って行っても愛想も何もありゃしないし。お節介はお断りだって顔に書いてあったわ」
(……それを読み取ってくれていたなら何よりだわ。どうぞそのまま私からは一定の距離を保ってちょうだい)
遠ざかっていく夫婦の声に、比奈子はほっと息を吐いた。
今の比奈子は、安穏とした己の生活をただひたすら守り抜くために生きる身だ。そのために時には一種の仮面をかぶる必要がある。つまり、全力で『なるべく深く関わりを持ちたくないような変わり者の隣人』を装うのだ。この町の片隅に埋もれて一人平和に暮らすために。
何しろ『夜闇の妖姫』の悪評が裏中務にまで届いてしまったのは、夜な夜な徘徊する比奈子の姿が近隣住民の間で瞬く間に噂になり、警保局に通報が相次いだせいでもあるのだ。今生では目立つ行動は避けながら、適度に遠巻きにされつつ、と言って過度に眉も顰められない程度の距離感を保たなくてはならない。要は積極的に触りたくはない小さな腫れ物の立ち位置に徹するのだ。例えば今の比奈子が演じている、往来でただ歩く時間すらも惜しむほどの本の虫というような。若い女の一人住まいというだけなら、ああして善意からくるありがた迷惑を押しつけられてしまう可能性があるが、変わり者を装っていれば彼らはある程度こちらを遠巻きにしてくれる。
家に着く頃にはあの三本足の烏の妖はもういなくなっているだろうか。いくら怪奇現象が起こる変な家とはいえ、野生の獣が人間の住まいに長居はしないほうがいい。
そういえば、と比奈子は口の端に柔く笑みを浮かべる。
一年ほど前にも、烏に似た妖を助けたことがある。雛が卵からうまく孵れず苦しんでいたので、孵化を手伝ってやったのだ。鳥の孵化を手助けするなど初めての経験だったので大変な緊張を伴う作業だったが、殻から取り出した小さな身体がきちんと呼吸しているのを見たときは心底ほっとした。あのときは三本足ではない、普通の烏の雛の姿をしていた。本当に妖ではなくただの烏なのかと思ったほどだ。妖だと判じた理由は、その卵の殻の色が烏とは違って漆黒だったからである。比奈子は妖にもその生態にも詳しいわけではないため、あれがどういう妖だったのかは今となってはわからないが、元気に成長していてほしいと思う。
帰宅し、買ってきた惣菜をおかずに朝食を取る。簡単な後片付けを済ませ、ついでに購入してきた食材も片付ける。
裏庭の梅の花でも見ながら一息つこうと茶を淹れ、茶菓子と一緒に載せた盆を持って縁側のほうへ向かう。
確かに三本足の烏はもういなくなっていた。ただしその代わりに、きなこのおはぎのような丸いものが同じ場所に落ちている。大きさもまるきり大きめのおはぎだ。目を凝らしてよく見ると、きなこ色をした小さなねずみのような獣が蹲っているのだった。
「もう、またなの?」
流石に少々うんざりしながら呟いてしまう。その声に反応してか、ねずみがこちらを振り向き、牙を剝いて威嚇してくる。怪我は見えないが、やはり興奮状態にあるらしい。
溜息交じりに茶を縁側に置いて、草履に両足を入れる。
本当は今生ではご近所付き合いだけではなく、妖とも関わらずに生きていきたかった。しかしこの土地と、比奈子自身の放っておけない性分がそうさせてくれなかった。
この土地は恐らく、悪い意味で『気』が強すぎる。家の中で怪奇現象が起こるのも、裏庭に弱った妖がしばしば引き寄せられて迷い込んでくるのも、すべてはこの土地が持つ何らかの呪力のようなもののせいだ。
何せこの土地は――かの悪名高い陰陽師、蘆屋道満の系譜にある谷木家が先祖代々受け継いできた場所なのだから。
土地の持ち主であるあの親戚も比奈子自身も、系譜の端の端にいるに過ぎない。いくら蘆屋道満が強大な力を持っていたとしても、普通に考えればこんな末端に至ってはその力は湖に一滴の墨汁を垂らす程度に薄まっているはずだ。
だが、何事にも相性というものがある。他の多くの者にとってはただ何となく怖い、何となく嫌な感じがする、という程度であったこの家で比奈子は、暴走状態の妖を落ち着かせるという異能とも呼べる力を開花させてしまった。恐らく比奈子は悪い意味でこの土地との相性が良すぎるのだ。兵庫の実家にいた頃には蓋がされていたはずの力が、この地で蘆屋道満の力の残滓を浴びたことによってその蓋が弾き飛ばされ、押し込められていたものが表に出てきてしまったというわけである。
比奈子は梅の木の下のおはぎ、もといねずみの妖に歩み寄る。
(仕方ないわよね。うちの敷地内なんだから放っとくわけにもいかないし)
何かに対して言い訳を並べながら、ねずみの妖に渋々手を伸ばす。
それでも前世での反省を活かし、塀や家の中のあちこちの壁に、納屋から発掘した古いお札を貼ってあるのだ。さすがは陰陽師の系譜というべきか、二階の納戸にはそういった護符だの何だのといった、先祖代々受け継いできたのであろう呪術の道具らしきものが大量に仕舞われていた。
比奈子にはその使用方法もありがたみもさっぱりわからないが、何となく手に取ったお札に、文字なのか絵なのかも判別できないような図案が描かれていた。それが何となく人間の目のようにも見えたので、目隠し用の結界のようなものかもしれないとあたりをつけ、家中のあちこちにぺたぺたと貼って回ったというわけだ。効果のほどはわからないが、一種の願掛けのようなものだった。
鋭い牙で噛みつこうとしてくるねずみの妖の視界を手のひらで覆い、柔らかい身体に手をあてる。毛並みの下から血流が大暴れしているのが手のひらを介して伝わってくる。
「あなたたちも厄介な習性を持ったわね。こんなふうに発作的に獰猛になったり、暴走したりしてしまうなんて。そのせいであんな白装束集団に目を付けられて殺されるなんて、ほんとやってらんないわよね」
前世ではただ助けてやりたい庇護対象だった妖たちに、こうして自分の境遇を重ねて感情移入までしてしまうのは、比奈子が一度殺されるところまで行ったからだろうか。
(身に覚えのない誰かの仇扱いされて、濡れ衣で殺されるなんてもうまっぴらだわ。それに正しいと思ってした行動を咎められるのも、私自身を否定されるのもまっぴら。せっかく手に入れたこの平和な暮らしを脅かされるのも絶対に御免よ)
ねずみの妖は比奈子の手の下でとろんと目を細めている。あれほど破裂しそうだった小さな身体が落ち着きを取り戻し、手のひらから心臓の穏やかな鼓動が伝わってくる。
比奈子はねずみの妖を抱き上げ、胸に抱いた。
そして強い眼差しで、記憶の中のあの白い軍服の男を睨めつける。
(今度は必ず生き延びてみせるわ。あの白装束集団――裏中務に万が一にも出会うことのないように、目立たず、誰とも交流を持たず、たった一人で今生を全うするのよ)
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




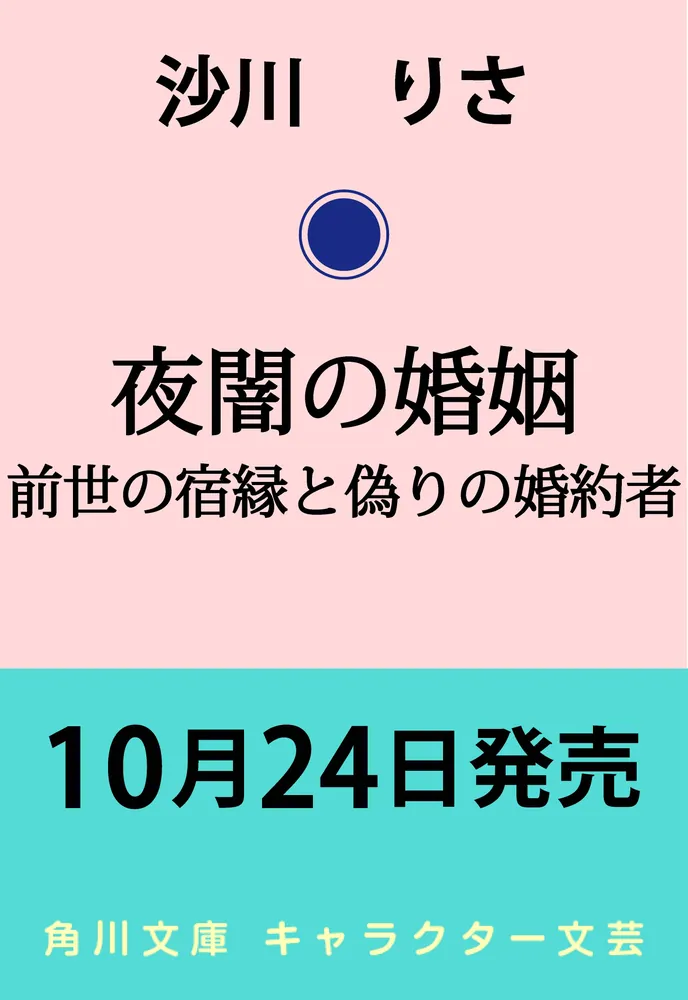
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます