第17話 日常。元には戻らないもの
学校帰りに、商店街の方へ足が向いた。
喫茶『南半球』に通じる路地の手前で、ゆっくりと立ち止まる。
あの喫茶店に、もう翔はいない。
従兄弟だという店長は、彼がいなくなってどうしているだろう。釣り銭を盗んでいたことを考えると、胸中は複雑だろうか。
翔の両親は、友人は、今回の事件をどう受け止めているのか。
知ったところでまつりにできることはないけれど、考えずにはいられなかった。
【オラクル】については、えにし堂と相談して、そのまま喫茶『南半球』で保管してもらうことになった。
店を守ってくれている呪物だが、そのせいで不穏な噂が流れて客足に影響が出ている。
まつりは、清流神社で引き取ることもできると、店長に申し出るつもりだった。
だがえにし堂は、【オラクル】自身が店を守るべき対象として捉えているのだから、引き離すべきではないだろうと言った。確かに、無理やり引き離せば逆に災いをもたらしそうな気もする。
えにし堂としては、呪物についての説明をして、今後店長の理解を求めていくつもりらしい。同じ商店街で店を経営しているとはいえ、彼にご近所付き合いができるとは思えない。つまり、必然的にまつりも同行することになるのだろう。
しばらく路地前で足を止めていたまつりだったが、やがて歩き出す。
商店街を抜け、家に帰るために。
だが、数歩もいかないところで、蒼司と瑞葉に出くわしてしまった。
妹はともかく、次兄はまずい。面倒なところで見つかった。
予想通り、蒼司の機嫌がみるみる下降していく。
「まつり。あの怪しい喫茶店に行っていたのか」
「おかえりー、お姉ちゃん。寄り道? 私は温太兄からお使いを頼まれたんだけど、ちょうど蒼兄にばったり会ったから手伝わせてたとこ。あーあ、どうせならお姉ちゃんと最初に出会いたかったなぁ」
「瑞葉、うるさい。今は話がややこしくなる」
末っ子の発言に色々言い返したいのをこらえて、蒼司はまつりを睨みつける。
「その道の先にはあの店しかない。言い逃れはできないぞ。えにし堂といい、怪しいところに出入りするなと何回言えば分かるんだ」
まつりは溜め息をついてから、瑞葉に向き合う。
「ただいま、瑞葉。買いものはもう終わった? 荷物持つね」
「ありがとう、お姉ちゃん」
「おい、俺を無視するな」
蒼司がすかさず視界に割り込んでくるから、まつりは溜め息をついて文句を返す。
「どこにも寄り道してないのに、そっちが言いがかりつけてくるからでしょ。大体、何で蒼司にそんなことを注意されなきゃいけないの。えにし堂が怪しいのは否定しないけど、喫茶店は危険区域じゃないよ」
「お前が、呪物があるかもしれないって言ったんだろうが」
正論だった。
劣勢を悟り、まつりはそそくさと歩き出す。
「……大丈夫。あれは危険のない呪物だと判明したし」
「呪物なら、危険かどうかは関係ないだろ」
「それって偏見。呪物だって、人を守る意図で作られたものもあるし……」
とりあえず話を逸らしたくて、まつりは雑貨店のショーウィンドウに目を留めた。
「あ、ほら。瑞葉の好きな、全肯定うさぎグッズがあるよ」
「おい、瑞葉を盾にするな」
可愛い妹を盾にするとは、人聞きが悪い。
まつりは斜に構えて蒼司を睨み返した。
「違います。私は瑞葉の喜ぶ顔が見たかっただけ、瑞葉がいれば白河家は安泰なんです」
これは白河家の共通認識だし、まつりにとっては昔からのすり込みのようなものだ。
白河家に来た当初、母親を恋しがる瑞葉を宥めると、家族全員が笑ってくれた。
そうやって、自分に役割があることはまつりの心のよりどころになったし、何より、瑞葉が泣き止んで笑ってくれると、こちらまで救われた心地になったのだ。
幼い彼女が抱える寂しさは、突然両親がいなくなったまつりにとっても、他人事じゃなかったから。
きっとまつりは瑞葉を慰めながら、自分の傷とも向き合っていた。
だから瑞葉が泣けば暗い気持ちになるし、瑞葉が笑えばほっとする。
彼女が幸せなら白河家はうまく回っていくと、まつりは本気で信じていた。
すると蒼司は、苛立ったように吐き捨てる。
「お前は本当にいつもいつも……俺の心配を何だと思ってるんだ」
「……心配? 怒ってるだけじゃなかったの?」
まつりは戸惑い、本音をこぼした。
――え? さっきの『呪物なら危険かどうかは関係ない』っていうのも……偏見じゃなくて、私を呪物に近付けないようにってこと……?
そこまで心配しているなんて、いつも不機嫌そうだから気付かなかった。
だとしたら、何度も彼を誤解していた。
不用意な衝突をしてしまったこれまでを、今さら悔やむ。まつりは、もっと蒼司の気持ちを思い遣るべきだったかもしれない。
咄嗟に言葉を出せずにいると、のんびりとした声が上がった。
「――お姉ちゃんって、分かってるようで分かってないよね」
瑞葉だ。彼女はまつりを見上げ、穏やかに微笑んでいる。
「まぁ、基本的には蒼兄の伝え方が不器用すぎるのが原因なんだけど。不器用すぎちゃって、もはや下手だよね」
人をからかうことの方が多い瑞葉だが、真面目な話をする時は雰囲気が変わる。
凛と大人びて、不思議と耳を傾けずにいられない空気をまとうのだ。
蒼司は何も言えなくなっている。
まつりもまた、吸い込まれるように彼女の美しい瞳を見つめていた。
「『瑞葉がいればいい』じゃないよ。誰が欠けても駄目なの。――お姉ちゃんも、だよ」
数年にわたって関係が悪かったので、蒼司の本心を知っても、正直気まずかった。
まつりだって彼の嫌みに少なからず傷付いてきたから、すぐには態度を変えられない。
けれど、そんなわだかまりが、瑞葉の柔らかな言葉によって洗い流されていく。今の彼女はいつもの無邪気さも鳴りを潜めており、ひどく達観して見えた。
まつりは、今度こそ素直に蒼司と向き合う。
「蒼司……あの、ごめん。今までも、誤解して……」
誤解の原因は蒼司の態度にもあるけれど、問題の大部分はまつりの頑なさだ。
今はそれを捨て去り、真っ直ぐに彼を覗き込む。
「ずっと……心配、してくれてたの……?」
「お、俺はただ、何かあれば家族が困るだけだと思って……」
いつもは顔を背けているから気付かなかった。
蒼司の頰が、真っ赤になっている。
まつりまで恥ずかしくなってきて、熱い顔を隠すようにマフラーの位置を直した。
再び、誰からともなく歩き出す。
普段なら蒼司と瑞葉の言い合いでも起こりそうなものなのに、次兄の口数がぐっと減っているためひどく静かだ。
まつりも熱さが落ち着いてきて、前を歩く瑞葉を改めて見つめた。
「瑞葉って、本当にしっかりしてるよね……」
何となくそわそわしてしまうのは、先ほどの台詞が妙に意味深だったからだ。
まつりと蒼司の間にある誤解を解くためであったのは確かだが、別の含みもあった気がしてならない。
【ほしいさま】のことは、瑞葉に詳しく説明していなかった。
警察が来たから全ては隠し通せないけれど、まつりと翔の間に何があったのか、【ほしいさま】が何をしたのか、まだ小さな妹に聞かせるには刺激が強すぎるからと、温太達と話し合って黙っておくことを決めていた。
それが、瑞葉の心を守ることに繋がっているはずだからと。
――私が危険な目に遭ったって……気付いてる、なんてことは、ないよね……?
気付いていないと思うのに、何だろう。圧がすごい。ばれたらまずいことになるという予感が消えない。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




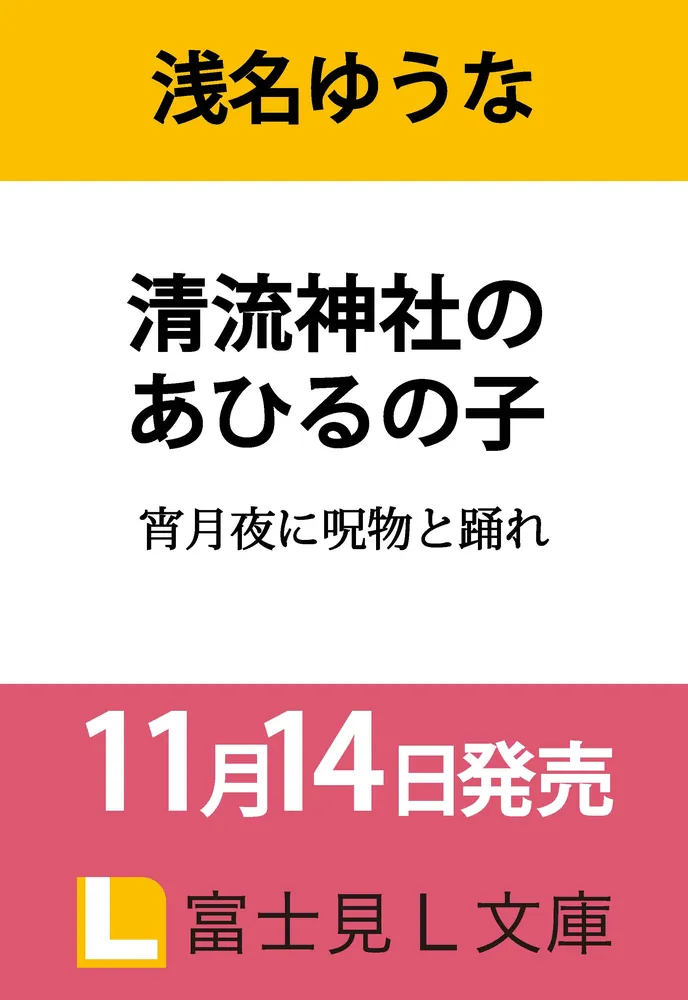
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます