第12話 温かさの奥底で
見た目は、木製の人形に服を着せ、麻袋をそのまま頭部にしたような素朴なもの。素朴なのに、顔の粗い縫い目がつぎはぎとなり、妙な凄みがある。目と口の部分は木目が露出しており、そこに何本か釘が打たれているせいだろうか。
古いものだが、丁寧に扱われてきたのだろう。着ている服も、長い手の指先近くまでしっかりと布で覆われているから、間違いなくこの人形のために作られたものだ。
「まつりちゃん? どうかした?」
人形を凝視していると、翔が不思議そうに問いかけてくる。
「すみません、何でもないです。色んな人形があって、興味深いなと思っただけで」
咄嗟に誤魔化すまつりに、翔は相槌を打つ。
「分かる。迫力ありすぎて、思わず拝みたくなるよね」
まつりは目を見開いた。
「呪物だと、分かるんですか?」
「えっと……呪物?」
「え……?」
「いや、拝むっていうのはたとえだよ。まつりちゃん、冗談通じないなぁ」
翔が呪物の存在に気付き『拝む』と口にしたのかと思ったが、まつりの早とちりだったらしい。
冷静になり、焦る必要はないと思い直す。
まつりの推測通り、呪物はあった。
だが危険なものではない。詳しいことまで覚えていないけれど、精霊の依代となる類いの呪物だったような気がする。
そうすると、無闇に呪物だと騒いで翔を動揺させることもないだろう。えにし堂に確認をとり、さらにこの喫茶店の店長の意図を聞いてからでも遅くはない。
「……すみません。実家が神社なもので」
言いわけにもならないような理由づけ。
だが笑顔でいた翔が、不意に神妙な顔付きになった。
「まつりちゃんのお家って、神社なの?」
「はい。近所の清流神社です」
「清流神社……その名前聞いたことあるな。もしかして、店長が『呪物神社』って言ってたところ?」
「ご近所さんにはそう言われてますね。悪い意味合いじゃなく、事実として」
近所の方々は、決して気味悪がって『呪物神社』と呼んでいるわけではないので、そこだけは強調しておきたい。ただの事実として呼んでいるだけ……のはずだ。
だが翔にとっては気にすることでもないようで、彼は何やら考え込みはじめた。
「そうか……『呪物神社』なら……」
その呟きは、やけに切羽詰まっている。
コーヒーを飲みながら静かに待機していると、ようやく翔が顔を上げた。彼は、深刻な表情で切り出す。
「あのさ、清流神社ってお祓いとかもやってるよね?」
「もちろんです」
頷くと、彼は声を潜めて続けた。
「うちの店長、怪奇現象が起きても問題ないって、何の対策もしてくれないんだ。でも店にいる時間は僕の方が多いから、正直不安でさ」
時給が高いからといって、不安がなくなるわけではないだろう。
まつりは先を促すように頷いた。
「本当なら店ごとお願いするべきなんだろうけど、店長の意向なら仕方ないし、せめて僕だけでも安心して働きたくて。今度の週末、清流神社でお祓いをしてもらってもいい?」
翔の申し出は、少々意外なものだった。
おしゃれで今どきな若者という印象で、信心深いタイプには見えなかったから。
――って、偏見はよくないか。
どこの誰にでも開かれているのが神社だ。
「分かりました。兄に伝えておきます」
まつりは翔の依頼をしかと請け負った。
結局その後も怪奇現象に遭遇することはないまま、喫茶店をあとにする。
一時間程度で帰るつもりだったのに、予定以上に長居してしまった。
喫茶『南半球』の外は、既に暗くなっている。
温暖化が進んでいるとはいえ、日が落ちれば秋の長野は急に冷え込む。だが長野県民は寒さに耐性があるため、装備している防寒アイテムはカーディガンくらいだ。
まつりはブレザーの裾を直しながら、見送りに出てくれた翔を振り返った。
「では、週末に」
「うん。まつりちゃん、相談に乗ってくれてありがとう。まだ何も解決してないのに、ちょっとだけ気が楽になったよ。今度サービスするから、よかったら友達も誘っておいで」
「そうですね。また機会があれば」
「あは。それ、絶対に来る気がない時のやつでしょ」
翔がおかしそうにしているから、まつりもほんのり笑った。
しっかり頭を下げてから歩き出す。
商店街を抜け、住宅地を進む。家まで十分もかからないだろう。
別れ際の翔を思い出す。
清流神社でお祓いをすることで、彼が少しでも安心してくれたら嬉しかった。
白河家の家業が、誰かの心を助けている。
少し誇らしくて、冷たい風を感じながらも、まつりの頰はゆるんだ。
今日の夕食は温野菜のサラダと、すりおろし林檎がたっぷり入ったカレーライス。
人参にさつまいもにかぼちゃ、まいたけやしめじも入ったサラダは、醤油ベースの玉ねぎドレッシングがよく合う。ドレッシングは温太の手作りだ。
ちなみに野菜と林檎もご近所からお裾分けしてもらったもので、全て節約料理だった。
「カレーおいしー」
「うん、おいしい。豚肉と林檎って相性いいよね」
小学生の瑞葉には、林檎で甘くなったカレーがちょうどいい。
甘いカレーが物足りない場合は、各自好みの分量でチリパウダーをかけるのが白河家流だ。スパイスで辛みを足しても、林檎のフルーティさが損なわれることはない。
ほくほくの温野菜も、秋ならではの味わいだった。ドレッシングに使われている醤油を一度加熱しているのか、香ばしい風味があとを引く。
「温太くんの料理って手が込んでるよね。おいしいし嬉しいけど、無理してない?」
特に今日は急な祈祷依頼が入ったと聞くし、料理の準備はたいへんだったはず。
心配して問いかけるまつりに、温太は得意げな笑みを返した。
「お前らが幸せそうに食べてくれるから、全く問題ないよ」
「そういう概念の話じゃなくて」
「概念とかじゃなく、マジで俺のやり甲斐なんだけど」
「……お母さん」
「ママ」
「おかん」
「うるせぇよ」
一しきり笑い、それが落ち着いたあと。
蒼司が改まった態度で切り出した。
「ところで、まつり。今日は帰ってくるのが遅かったな」
まつりは内心でぎくりとした。
けれど問い質される予感はしていたので、表面上は冷静に対応する。
「うん、まぁ。温太くんには事前に伝えてあったよ」
「ってことは、急に友達と遊びに行く流れになったとかじゃなく、計画的な寄り道だったってわけか」
まずい。神社の手伝いをサボったと誤解されたくなくて先回りしたはずが、逆に自分に不利な情報を与えてしまったらしい。
咄嗟に目を逸らすと、蒼司は逃さないとばかりに顔を寄せてくる。
「行ったんだな」
圧に負け、まつりはすぐに開き直った。
「……行かないって約束してないし。大体、何で蒼司に怒られなくちゃいけないの? 門限があるわけでもないのに」
言い返すと、蒼司はいつもの不機嫌顔でぐっと黙り込む。
沈黙が落ちた居間に、瑞葉の忍び笑いが響いた。
「蒼兄、伝わらないね」
「うるさい」
蒼司は苦い顔で末の妹を睨んでから、改めてまつりに向き合った。
「門限とかそういう話じゃない。俺はそもそも、お前があの怪しげな骨董店に通うのも反対なんだ。何で自分から呪物だの心霊スポットだのに関わろうとする?」
「……うちの神社には呪物が集まってくるんだから、知っておいて損はないでしょ」
まつりは、食べ終えた食器を片付けはじめる。
これ以上追及されたくない。
さっさと居間から出て行こうとするまつりを、蒼司の声が追いかけてくる。
「おい、まつり。まだ話は終わってないぞ。席を立つんじゃない」
次兄の口振りに、傍観していた瑞葉が噴き出した。
「温太兄がお母さんなら、蒼兄は頑固親父だね」
「が、がんこおやじ……⁉」
親父扱いに衝撃を受ける蒼司に、温太が声を上げて笑う。
「確かに頑固親父っぽいな。俺もせっかく作ったんだから、料理に何か一言くらいコメントが欲しいもんだし。――ね、あなた」
「やめろ!」
「夫婦喧嘩」
「やめろーー‼」
笑いの餌食にされている蒼司を置き去りにして、まつりは廊下に出た。
途端、しんと冷えた空気が全身を包んだ。
笑い声が絶えない温かな居間から隔てられた寒々しさが、まつりの体を震わす。
両親の死についての疑問は、誰にも相談していない。
家族を守りたいからこそ、話すつもりはなかった。
両親の死因は心臓発作。
全くの健康だった二人が、一ヶ月という短い期間で立て続けに倒れ、そのまま還らぬ人となった。
悲しみを乗り越え、成長したまつりは、そこに疑問を抱くようになった。
もしかしたら、両親の突然死は、呪物のせいだったのでは……と。
本当は、それを確かめるため、呪物について学んでいる。いつか何かしらの手がかりが得られるのではないかと、えにし堂に通い続けているのだ。
――それに……。
白河の父・潤の豪快な笑顔が甦り、ぎゅうっと胸が痛んだ。
まつりは息を吐いて、その重苦しさをやり過ごす。
そうして、一人静かな廊下を歩き出した。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




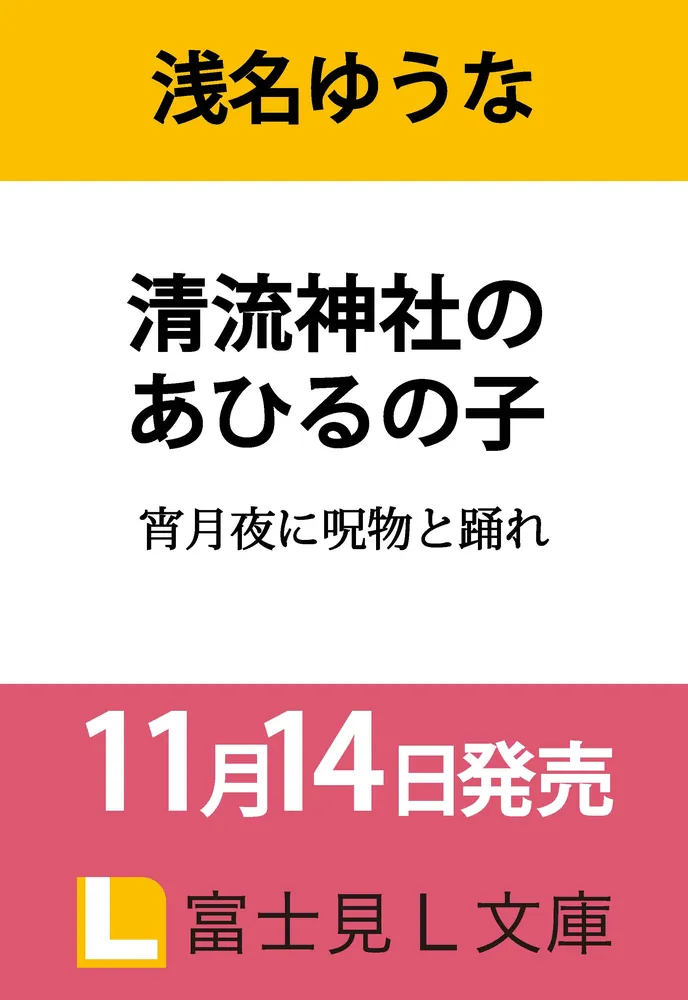
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます