第二章 険しい契約結婚⑧
――琉河は勿論、障子戸が締め切られて家の中と断絶されたままの裏庭のほうにも、ずっと注意を配っていた。裏庭が特に気になったからというわけではない。そこも監視対象の敷地内であるから当然のこととしてだ。
それが六日目の朝、思わぬ形で実を結んだ。
裏庭に佇む見事な梅の木のほうから、獰猛な妖の微弱な殺気を感じ取ったのだ。もし自分が玄狼党の狼の妖だったら、即座にそちらに対峙し牙を剝かねばならないほどの殺気を感じていただろう。
「障子戸を開けさせてもらうぞ」
琉河は比奈子にそう断ると、裏庭とを区切る障子戸に手を掛けた。比奈子は怪訝そうに少し眉を顰め、どうぞ、と答えた。
戸を開け放つ。裏庭の奥に見事な枝振りの梅の木があり、美しい花を咲かせている。果たしてその根元を一匹の小さな猫がよろよろと歩いていた。琉河の強い警戒心に一瞬こちらを向き、威嚇してきたが、そのまま素早くどこかへ逃げ去っていった。すぐに姿を消してしまったからよく確認できなかったが、後ろ足が赤く染まっているのがちらりと見えたから、恐らくは弱っているのをこちらに隠すためだろう。
怪我をしているのが見えなかったとしても、その猫の尾が二又に分かれていたことに――ただの猫などではないことに気付かないはずはない。
比奈子がどんな反応を示すのか、琉河はただ窺う。こちらから何かを言って相手の答えを誘導するのは悪手だからだ。
すると――比奈子は微笑んでみせた。
「きれいな梅でしょう?」
予想外の言葉に、琉河は思わず目を見開く。
「……何?」
「あら、あなたお花には興味のないたちなの? 私、特に梅や桜を見るとなんだか切なくて胸が痛くなるのよ。こんなにきれいな花を咲かせてもすぐに散ってしまうのね、って」
だから、と比奈子は切なげに障子戸を指さした。
「その戸、閉めてくださらない?」
琉河は息を呑んだ。
「……ああ。わかった」
障子戸を閉める。比奈子はそれを切なげに見届けてから、台所のほうへと向かう。
「お茶を淹れるけど、あなたも飲む?」
「いや、俺のことは気にするな。いないものとして――」
「あなたいつもそう言うけれど、この際言わせていただくわ。そんな大きな身体で常に視界の端にいられちゃ、気にしないなんて不可能よ」
琉河は別段大柄というわけでもないはずだが、比奈子は軽口のようにそう言い残して、水を入れたやかんを火にかけ始めた。
その細い背中を、琉河は睨みつける。
(この女……まさか妖に気付いていないのか? いや、そんなはずはない。だが気付いていながらあんなに平然とした態度でいられるものか……?)
疑念は急速に膨れ上がっていく。
――人との関わりを断って生きてきた比奈子は、妖というものが一般人であっても見えはするのだということを知らなかった。妖を見た人間の記憶が書き替えられるだけなのだということを知るすべなど、前世でも今生でもありはしなかったのだ。
(うまくやったわ、我ながら)
茶葉を蒸らしながら比奈子は内心で拳を握り締めた。
翌日も、その翌日もまた琉河は裏庭に続く障子戸を開けていいか比奈子に問うてきた。比奈子は胸中で舌打ちしながらも、顔では微笑みながら快諾してみせた。そのたびに梅の木の根もとには妖がいて、比奈子はその痛々しい姿に胸を痛めながら、早く立ち去ってくれと心の中で願った。
――琉河の疑念は日を追うごとに強くなっていったが、同時に混乱も極まりつつあった。
妖に気付いていない、否、見えていない様子なのにも拘らず、それ以外の点ではなにひとつ不自然なことも疑わしいことも見当たらないのだ。限りなく一般的な普通の人間に近いはずなのに、妖が見えていない素振りをするというただ一点において大きすぎる違和感がある。
だが、それだけなのだ。
比奈子が妖を集めようとしたり、何かを命令したりしようとしている様子は一切ない。妖たちのほうも、負の気脈に沿って歩いていたらたまたまここに迷い込んでしまった、というふうなのだ。どの妖たちも今にもこちらに襲いかかってきそうなほど気が立っている様子ではあるが、野生の獣の性として怪我を隠そうとしてか、すぐにそのまま姿を消してしまう。どの妖たちも犬猫ほどか、それより小さいものばかりなので、琉河の威圧的な気配から本能的に「勝てない」と感じて逃げ出しているのだろう。
妖が目の前にいるのに討伐せずに見逃すというのは、琉河にとっては非常に苦しいことだった。琉河自身の目的に繋がる手掛かりをみすみす取り逃がすのと同義だからだ。この家の敷地に迷い込んできた妖がまた出て行くということは、その後その妖によって犠牲になる人間が出てしまう可能性があるということでもある。しかも相手は気が立っている、獰猛な状態の妖だ。犬猫以下の大きさならともかく、大型の妖ともなれば、丸腰の人間などひとたまりもない。
どこか歪な緊張感を引きずり、ぎすぎすとした空気のままさらに矢のように三日が経つ。
そして――十日目の朝、ついに事件は起こった。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




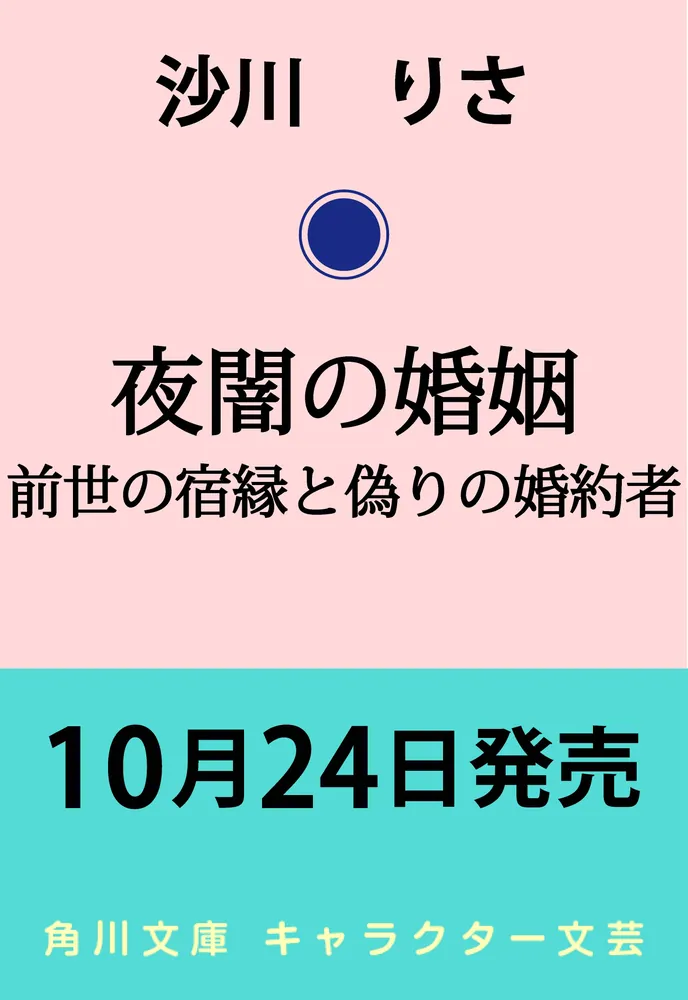
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます