第一章 再びの生⑪
「それに正式に名指しで俺が任命されている。もし俺が嫌だと言ってもこの命令には逆らえない。何しろ俺は公務員だからな」
意趣返しのようにそう言われて、比奈子のこめかみがぴくりと反応する。肌がひりつくような緊張感が押し寄せてきて、内心焦りが募っていく。
――今のでこちらは万策尽きたのではないか。この男を追い返す手段がこれ以上はもう思い浮かばない。
(諦めたらだめ。こちとら命と、平和で安穏とした悠々自適の隠居生活が懸かってるのよ!)
こうなったら背に腹は代えられない。比奈子は覚悟を決めた。面と向かって正々堂々と大嘘を吐く覚悟を。
どん、と足を踏みならす勢いで琉河に詰め寄り、その顔をきっと睨みつける。
「あなたが公務員だというなら、私はこの谷木家を守る主です。先祖代々この土地には家族以外は入れてはいけないときつく言いつけられているの。だから私は近隣との親交も持たないし、この家には誰の出入りもないのよ」
よくもまあ咄嗟にここまで出任せを並べられるものだ、と自分自身に感心しながら、高らかに言い放つ。
「家族でもない、ましてや将来を約束した恋人でもない人をこの家に入れるわけにはいかないわ。――この家の主として、我が谷木家の掟に従って!」
真顔で尤もらしい嘘を毅然と吐き、比奈子は胸を反らし、両手を広げた。この家に入りたければ私を倒していけと言わんばかりに。
しばし睨み合いが続き――先に折れたのは琉河のほうだった。
「……わかった。そういう事情ならば仕方ない。そこまで調べを付けていなかったこちらの落ち度だ」
勝った、と比奈子は内心で確信した。拳を突き上げたい衝動をおくびにも出さず、鷹揚に頷いてみせる。
「わかっていただけたのならよかったわ。どうぞお引き取りくださいな」
「ああ。今日のところは失礼する」
琉河はそう言って、ふと自分の首に掛かったままの手拭いの存在を思い出したのか一瞬そちらを見下ろした。何か言われる前に、と比奈子は先回りして答える。
「差し上げるわ。元より頂き物で溢れているからお返しいただかなくて結構よ」
無論、もう二度と顔を合わせたくないが故の方便だ。だが琉河は額面通りに受け取ったのか、軽く会釈してきた。
(そんなのいいからさっさと裏中務へでもどこへでも帰ってちょうだい!)
顔に笑みを貼り付けたまま内心で足を踏みならす比奈子に、しかし琉河はまだ帰ろうとしない。
それどころかまったく予想外のことを問うてきた。
「独り身の理由は手続きが煩雑だからか?」
咄嗟に何を問われたのかわからず、慌てて自分がさっき吐いた嘘を思い出す。比奈子がこの家に誰の出入りもない理由を谷木家の掟に絡めたから、そのことを言っているのだろう。
何かを疑われているのだろうか、とひやりとする。ここまできて、存在しないはったりの掟だと悟られるわけにはいかない。
ここは日頃から対外的に演じている『変わり者』の皮をかぶるのが得策だろう。咄嗟の嘘に咄嗟の嘘を塗り重ねるより、成熟した嘘を重ねたほうが真実味が増すはずだ。
比奈子は大儀そうに後れ毛を耳に掛けながら、つっけんどんに答えた。
「違うわ。一人でいたいからそうしてるだけ」
「一生独り身のつもりなのか」
「ええ、そのほうが自由でいいわ。他人に人生を左右されるなんてまっぴら」
これは前世を踏まえた心からの言葉だった。だから口先だけの誤魔化しではなく真に迫った回答だったはずだが、琉河はやはり何の感銘も受けた様子もなく淡々と答える。
「ならば離縁の傷が一度ついても、その後の人生に支障はないな」
「……はい?」
「支障はないな?」
まっすぐ目を見て念を押される。
何だかおかしい。話が妙な方向に転がろうとしている。そう思うのに、では具体的にどう答えるのが得策なのかを思いつけない。
「……まあ、私の離縁歴を気にする人なんて誰もいないけど……私含め……」
もごもごと答える。なぜこの男はそんなことを問うのだろう。
しかしその答えが出るより先に、今度こそ琉河は軽く会釈し、そのまま立ち去っていった。
半ば呆然と、不吉な白装束が通りの向こうに消えるのを見送り――三和土に残る水の跡をぼんやりと眺めているうち、ふつふつと比奈子の中に実感が湧いてきた。
(……私、あの男を追い返した?)
最後に不可解なやり取りはあったものの、とにもかくにもあの男は去っていったのだ。
(……やったわ! あの男を追い払ってやった!)
前世ではあの男と初めて相まみえたときが、即ち比奈子が殺されたときだった。
それが今生ではどうだ。自分はあの男を見事退けてみせたのだ。
(今度はあんたなんかに殺されてやるもんですか、絶対に! 私の人生から消え失せて、もう二度と関わらないで!)
今生での己の人生を己の手で守った充足感で座り込んでしまいそうだ。
それでも勝利を確信して陶酔しきることは、なぜだかできなかった。こんなに喜ばしい日だというのに、最後にあの男と交わしたやり取りが頭の隅に、見て見ぬ振りをするにはあまりに大きな存在感を持って引っかかっていたのだ。
比奈子のその懸念の答え合わせをするかのように、一週間後、掛井琉河は再び比奈子の家へとやってきた。
その日も朝からあの妙な落ち着きのなさに悩まされていたから、さすがに比奈子も、自分の中にある力が掛井琉河という人生の敵の接近を意識の外で察知し、危険を比奈子自身に伝えていたのだと悟るしかなかった。そしてそんな比奈子の様子を面白がるように、あるいは煽るように、比奈子をからかうこの家の怪奇現象も普段より悪化していたのだ、と。
玄関で琉河と再び相まみえ、呆然と立ち尽くす比奈子の目の前に、琉河はまた書類を突きつけてきた。今度はあの令状ではない。見覚えのありすぎる署名が入った、見覚えのなさすぎる書類だ。
署名は、この家の本来の持ち主である遠縁の親戚のもの。同じ谷木姓で、夫婦連名の署名である。
「実の両親とは絶縁状態で、この者たちがお前の後見人であることに間違いはないな?」
間違いはない。だがその署名がされている書類が大間違いだ。
「……ど……どういうことなの、これは」
「見ての通りだ。この家で任務を遂行するための手筈を整えさせてもらった」
眩暈がする。書かれている文字がうまく頭に入ってこない。全身の血の気が引いていく。
突きつけられた書面には――後見人の正式な署名と捺印入りで、目の前にいる掛井琉河と比奈子の婚姻を承諾する、と記されていたのである。
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




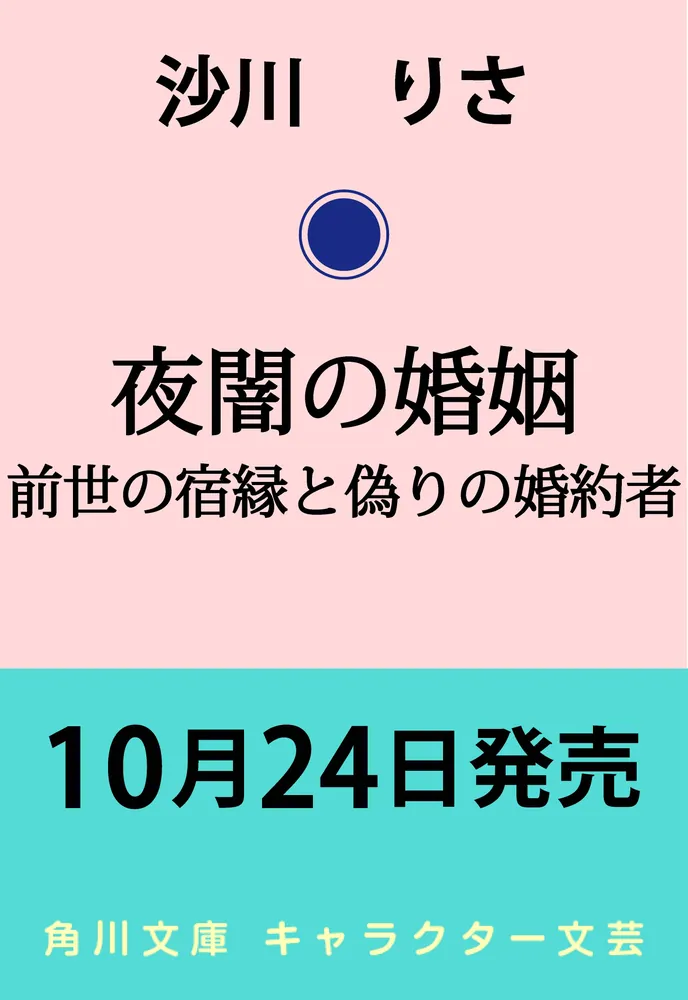
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます