第一章 再びの生⑨
比奈子は素早く思考を回転させると、顔を上げ、微笑みを浮かべてみせた。そしていつぞや読んだ本に登場した、何事にも動じず口も達者な女性主人公のように取り澄ました態度を取ってみせる。これもまた対人関係において自分が不利にならないよう立ち回るための、比奈子お得意の仮面のひとつだ。
「手拭いを取ってまいりますわ。ここでお待ちになっていてくださいね」
なるたけ無害そうに、なるたけ人が好さそうに見えるようそう告げて、比奈子はそそくさと手拭いを取りに戻った。今は何も考えずに不躾な振る舞いの謝罪だけして、さっさとお帰り願うしかない。
持っているものの中で一番見栄えのいい手拭いを手に取り、比奈子は急いで玄関に戻った。
そして悲鳴を上げた。
琉河が濡れた上着を脱ぎ、その下のシャツの釦まで外していたからだ。筋肉で隆起した胸もとが露わになっている。
琉河は真っ赤になってわなわなと震えている比奈子に怪訝そうな一瞥を寄越してくる。
(嘘でしょう!? なんて不躾な男なの!?)
自分の不躾は棚に上げて、比奈子は手拭いを叩きつけるように琉河に投げた。そして勢いよく背中を向ける。
琉河は叩きつけられた手拭いを摑んで目を瞬かせていたが、比奈子の態度にようやく己の行動を省みる気になったようだった。
「し――失礼した。上着の中までずぶ濡れだったからだ。他意はない」
あってたまるもんですか、と危うく叫び返しそうになったが何とか堪えた。
「か、身体が拭けたらお引き取りくださいませね。いろいろと立て込んでますの、玄関が終わったら次はお風呂場のお掃除も――」
「悪いがそういうわけにはいかない」
言葉を途中で遮られ、途端に嫌な胸騒ぎが沸いてくる。
今朝からずっと感じていたあの落ち着かなさを最上位まで高めたような感覚だ。
「警保局預の者だと言っただろう。俺はとある任務のためにここにいる」
「……おっしゃる意味がよくわかりませんわ」
冷たい汗で背中がじっとりと濡れる。掛井琉河は比奈子が裏中務のことをよく知らないと思って警保局のほうを――つまり警察組織の一種だというほうを強調したのだろうが、比奈子は無論、裏中務の任務がいかなるものかを知っている。
(まさか……どうして? 今生では殺されなきゃならないような行動はしていないはずなのに……!)
琉河のほうを振り向くのが怖い。こうしている今まさに、この男は比奈子の背中に軍刀の鋭い刃を突きつけているかもしれない。
「そちらにとっても大事な話のはずだ。顔を見て話をさせてくれないか」
比奈子はごくりと唾を呑んだ。その音が琉河にも聞こえるほど響き渡ってしまったように思えて、また胸中で舌打ちする。
意を決して振り向く。
しかしそこには覚悟していた凶刃はなかった。
依然として釦が開きっぱなしのシャツに、肩から手拭いを掛けた姿で、こちらをじっと見据えている掛井琉河がただ立っているだけだ。
ずぶ濡れの上着を着込んでくれとは言えず、比奈子は観念して琉河に正面から向き直った。目をまっすぐに見返す度胸も何となく湧いてこず、と言って剝き出しの胸もとに目をやるわけにもいかず、相手の口もとから首のあたりにかけてにぼんやりと視線を向ける。
そこでようやく比奈子は気付いた。
(……ないわ。あの傷跡が)
比奈子が死に際に相まみえた琉河には、その首から腹にかけて無数の傷跡があった。恐らくは比奈子側についていた妖たちとの戦いが激化した際、妖たちの牙や鉤爪によって負ったのであろう傷だ。
その傷が、目の前の掛井琉河にはない。
(ということは――私に味方する妖たちとこの男は、少なくともまだ対立していないってことだわ。一年先にどうなっているかは何とも言えないけど)
第一、今の比奈子には自分に味方する妖など存在しない。この家の敷地に迷い込んでくる妖をひととき休ませ、そのまま通り過ぎさせるための止まり木に過ぎないのだから当然と言えば当然だ。助けられた妖たちが必要以上に比奈子に対して恩義を感じたりしないよう、比奈子のほうも異能によって妖の暴走を鎮めた後は、なるべく突き放した態度を取るようにしている。
比奈子は思わず琉河の顔を見た。琉河の目はやはり、初対面の人間に対する警戒のようなものは浮かんでいるものの、妹の仇などというまったく身に覚えのない罪をこちらに着せてきたときの強い憎しみは欠片も見当たらない。
しかし同時に、比奈子が話を聞くまでは頑としてここを動くつもりはない、という意思も伝わってきた。
(……この男はまだ私を敵として認定していないんだわ。だったら、今ここで私が躍起になって追い返そうとするのは悪手かもしれない。却ってこちらにやましいところがあると言っているようなものかも)
であらば今比奈子がすべき行動はひとつだ。
琉河の話を聞くふりをして、妖に関することには知らぬ存ぜぬを突き通し、とにもかくにもしらばっくれ続ける。何の罪もない無害な一市民を装うのだ。そうして良き頃合いが来たら、その機を逃さず今度こそお引き取りいただく。それしかない。
比奈子は微笑み、小首を傾げてみせた。
「わかりました。ひとまずお話を伺いますわ。私ごときに何かお役に立てるようなことがあるとは到底思いませんけれど。何でしたかしら、ええと……裏中務とやらおっしゃる方の」
琉河は比奈子の顔をやはりじっと見つめている。こちらの真意を測ろうとしているのだ。一瞬でも気を抜けばすべてを見抜かれてしまいそうな強い眼差しである。
しかし比奈子も伊達に幼い頃から魑魅魍魎――文字通りの妖ではなく人間の皮を被った――の相手をしながら生きてきたわけではない。肝のひとつも据わっていない女に、特に前世を含めたこの壮絶な人生を生きることなどできないのだ。
「任務というのは、一体どういったものなのかしら」
触れれば電流でも走りそうな緊張感の中、片や微笑みを浮かべ、片や厳めしい顔で睨み合う。
先に視線を外したのは琉河のほうだった。手に持った上着の内ポケットから、きれいに折りたたまれた書面を取り出す。言うまでもなくしんなりと湿っている。
琉河はそれを破らないよう注意深く開いて、文字が書いてある面を比奈子のほうに向けてきた。上着の生地が上等なのが幸いしたのか、文字が滲むほど水は染みずに済んだらしい。比奈子は促されるまま文字に視線を落とす。
それはどう見ても、何かの令状のようなものだった。内務省警保局の捺印と、桐野という人物の署名がある。書かれている内容を読み進めるにつれ、比奈子は自分の全身がまた冷えていくのを感じた。
信じられない面持ちで琉河の顔を見上げる。
「……どういうこと? これは一体何?」
自分の目で読んだはずなのに、頭が理解することを拒否している。
琉河は令状をこちらに突きつけたまま、死刑宣告さながらの重々しい口調で告げた。
「谷木比奈子。お前が居住するこの家の敷地すべてが裏中務の監視対象として定められた。監視は原則として一日あたり二十四時間、つまり丸一日だ。そして監視終了日は未定である。こちらが成果ありと判断するまで続くと思っていただきたい。そして――」
蒼白な顔で見上げる比奈子に、さらなる追い打ちが、有無を言わさぬ圧とともに降りかかった。
「――その監視官はこの俺、掛井琉河が務める」
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




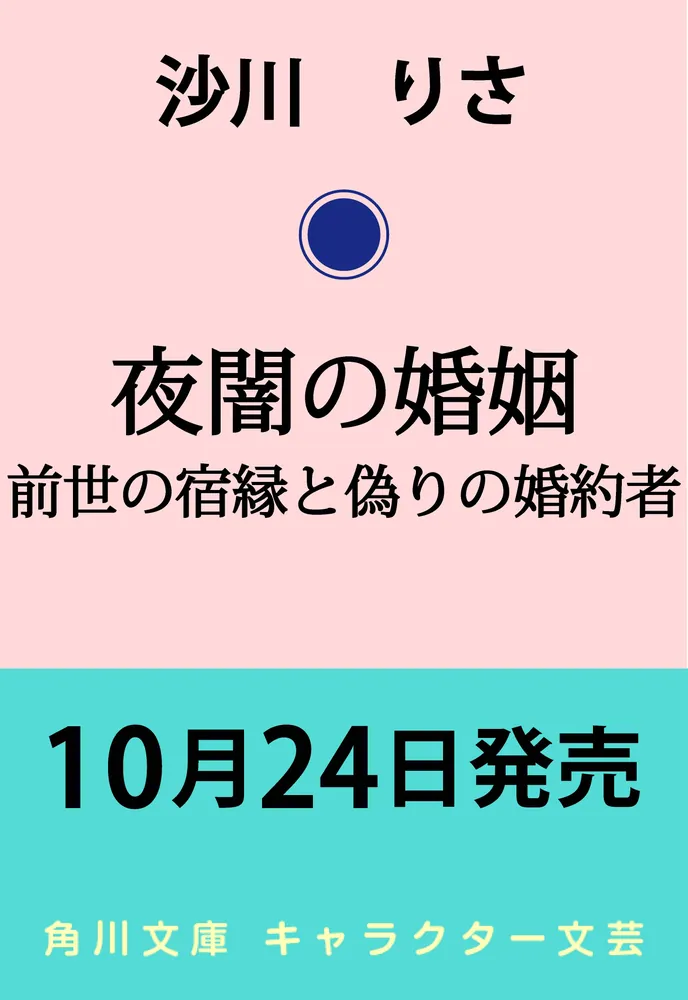
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます