第一章 再びの生②
最初にこうして傷ついた獣を助けたのはもう随分前のことだ。
――十年前、十三歳の頃に、比奈子はこの帝都の家にたった一人でやってきた。
生家は兵庫にある。
特別裕福でも貧しくもないごく普通の家庭に生まれた。両親も普通、家も普通、四つ下の弟も普通だった。普通でないのは比奈子ただ一人だけだった。
実家で暮らしていた頃の比奈子は、それでも今よりはまだ普通だったと言える。三本足の烏をはじめとした妙な生き物を見たことも、暴走状態にあるそれらに手をあてて落ち着かせてやったことも一度もなかったからだ。この力の――傷ついた獣を落ち着かせるのを力と呼ぶならば――存在に気付くことも、そのきっかけもなかった。
ただ、両親からは蛇蝎のごとく嫌われていた。
今思えば、娘の内に眠る力の片鱗を両親は無意識に感じ取っていたのかもしれない。それも本能的な恐怖とか、生理的な嫌悪感といった形で。比奈子は子どもの頃から他の同年代の子らよりも精神的に成熟しており、性格的にも決して愛嬌のあるほうとは言えずどこか冷めたふうな顔つきをしていたから、それが両親の比奈子に対する嫌悪に拍車を掛けていたのかもしれない。
両親は弟が生まれてからは比奈子のことはほぼ育児放棄状態で、弟ばかりを可愛がった。そればかりか比奈子を召し使い扱いする始末だった。弟のほうもその状況に甘んじて、次第に両親に倣って比奈子を見下すようになった。嫌うならいっそ追い出すなりして遠ざけてしまえばいいのに中途半端な人たち、と比奈子はやはり冷めた目で彼らを見ていた。
そういった経緯から、比奈子は早々に家族を見限ることにした。
実行するのを十三歳になるまで待ったのは、その年に身長がぐんと伸びたからだ。これで家出をしても、見るからに子どもだからと誰かに見咎められ無理やり家に帰される可能性も少しは低くなるだろうと考えた。
帝都を選んだ理由は、そこに唯一交流のある遠縁の親戚夫婦が暮らしていて、何軒かの空き家を所有しているのを知っていたからだった。その親戚は実家での比奈子が置かれた境遇を知っていて、尚且つ表向きは憐れむような素振りを見せていたので、こちらも頼りやすかったというのもある。ただしその理由は、その親戚が優しいから頼みを聞き入れてくれるだろうと思ったからではない。幼い少女が実の家族から受けている扱いを知っていながら、救いの手を差し伸べるでもなく、その上自分はちゃんと可哀想に思っているという顔だけはする狡猾な相手になら、こちらとしても相手を利用することに罪悪感を抱かなくて済むと思ったからだ。
実際、その親戚夫婦は一人はるばる帝都までやってきた比奈子を見るや、心底気の毒そうな態度を取ってみせた。そして持っている空き家のうちのひとつを示し、管理してくれるならぜひ住んでほしい、と言った。家賃はいらないし必要な修繕費は出すから、と。
それがこの家だ。
比奈子が初めてやってきたときには、この家は今にも倒壊寸前の廃墟のように見えた。実際もう何年も誰も住んでおらず、朽ちて崩れてしまわない程度の最低限の手だけは時折入れているがそれも形だけ、という様相だった。建て替えをしようにもこの土地に住みたいという人間がなかなか現われないのだという。
この家が建つここは、先祖代々受け継いできた土地なのだそうだ。
上物は何度か建て替えられてきたらしいが、そう説明する親戚のどこか泳いだような目は、比奈子にどこまで説明したものか決めあぐねているように見えた。というより、有り体に言えば明らかに不都合な事実を隠そうとしている様子だった。
その理由を、比奈子はこの家に住み始めて数年経ってからようやく知った。
この土地には――
それも負傷していたり、気が昂って暴走状態にあるような、要は何らかの理由で弱っている妖だ。例えば今比奈子の手の中にいる、片翼が抉られた三本足の烏のように。
(もっともこの摩訶不思議な動物たちが『妖』だったなんて、当時の私は知らなかったわけだけど)
今思えばあの親戚夫婦は、この敷地内に悪い気のようなものが集まっているのを知っていたのだろう。その悪い気にあてられてか、あるいは惹かれてかはわからないが、弱った妖たちが集まってくるのだ。親戚が妖の存在まで知っていたかどうかは不明だが、それでもこの土地に不気味さや嫌悪感を抱いてはいたのだろうと思う。両親が比奈子に対してそうであったように。その負債を、不意に飛び込んできた比奈子に、これ幸いと体よく押しつけたというわけだ。
あの全身が毒気に満ちていた父方の親戚である。「家出をした子があの呪われた土地で野垂れ死のうが知ったことではない」とでも思っているのだろうな、と穿った見方をしても仕方がないと思う。
(それに、利用したのは私も同じだものね)
この土地を手放したかった親戚は比奈子を利用し、そしてとにかく実家から離れたかった比奈子もまた親戚を利用した。お互い様だ。
名目上は住み込みの管理人だが、比奈子は実質この土地を上物ごと譲り受けた形である。家の中にあるものは使うも売るも捨てるも自由にしていいと言われていたから、ひとまずの生活を立ち行かせるのに必要なものを買うために、価値のありそうな古いものを見繕って質に入れた。十五歳になると隣町の商店に働き口が見つかったのでそれで活計を立てた。二十歳の頃、客の男に太腿を撫でられてかっとなりその横っ面を引っ叩いたのを店主に咎められ解雇された。五年務めた比奈子より、大口の客であるその男のほうに店主が阿った結果だった。
しばらくはやることを失って途方に暮れていた。が、途方に暮れるのにも飽いて、ふと思い立ち家中をひっくり返して大掃除してみた。するとなんと床下に多額の埋蔵金、もとい前の住人のものであろう貯金を発見した。ざっと見ただけでも、比奈子一人が質素に暮らすなら老後まで何とか食べていけそうなほどの金額があった。それ以来、比奈子は所有者の「家の中にあるものは使うも売るも捨てるも自由にしていい」の言葉を免罪符に、誰のものとも知れない財産を細々と切り崩しながら、実に質素に慎ましく暮らしている。
妖の姿を初めて見たのは、そんな生活を始めてすぐの頃だ。
それまで遭遇したことがなかったのはきっと、比奈子が忙しく出たり入ったりを繰り返していたからだろう。仕事を辞め、食料品や日用品の買い出しや散歩以外はほとんど外に出ない生活になったことで、単純に敷地内に迷い込んでくる妖と行き会う確率が上がったというだけで、恐らくはこの家は最初から妖が迷い込んでくる化け物屋敷だったのだ。
三本足の烏の雛は、比奈子の手の中でもうすっかり寝入っている。きちんと休めているようだから、傷もきっとすぐに治るだろう。あのまま興奮状態で暴走を続けていたら治るものも治らないし、人間を襲ってしまわないとも限らない。
妖が人間を襲ってしまったら、その妖は討伐対象になる。
この三本足の烏のように、本来ならば人間を襲ったりしない穏やかな性質の妖でさえ。
三年前、妖と遭遇し始めてからすぐに、比奈子は自分に何らかの力が備わっているのかもしれないと気付いた。
自分が触れると妖の気性が穏やかになる。正しくは、もとの穏やかさを取り戻す。酩酊により普段よりも荒々しく暴力的になっている酔っ払いが、急激に酔いを醒まして冷静さを取り戻す様に似ている。同じく人間で喩えるなら、普段は犯罪を犯すなど考えられないような穏やかで常識的な人が、普段飲まない酒を飲まされて悪い酔い方をしたせいで我を忘れ、とんでもない暴力沙汰を起こしてしまい、死罪になる――そういう取り返しのつかないことになる前に、その酔いを醒ましてやり、事態が悪いほうへ転がってしまうのを食い止める。比奈子がしているのは要はそういうことだった。
この手に癒しの力などというものはない。手を翳しただけで傷まで治してやれればいいのに、と何度も思ったけれど、比奈子にできるのは妖の状態を興奮から鎮静へと戻してやることだけだ。そうして身体を休められる状態にしてやり、妖自身の回復力でもって傷が癒えるまで一定期間ここで匿うだけ。
比奈子は三本足の烏を両手に載せたまま再び立ち上がり、梅の木の根もとにその身体を横たえてやった。どこからか入り込んできたこの妖は、元気になればまたどこかへと出て行くだろう。
「また飛べるようになったら気を付けて帰るのよ。白装束の集団に見つからないように」
脳裏にあの白い軍服姿の、鋭い目をした男が浮かぶ。
比奈子は深く息を吐き、呟いた。
「私みたいに、……殺されてしまわないように」
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。




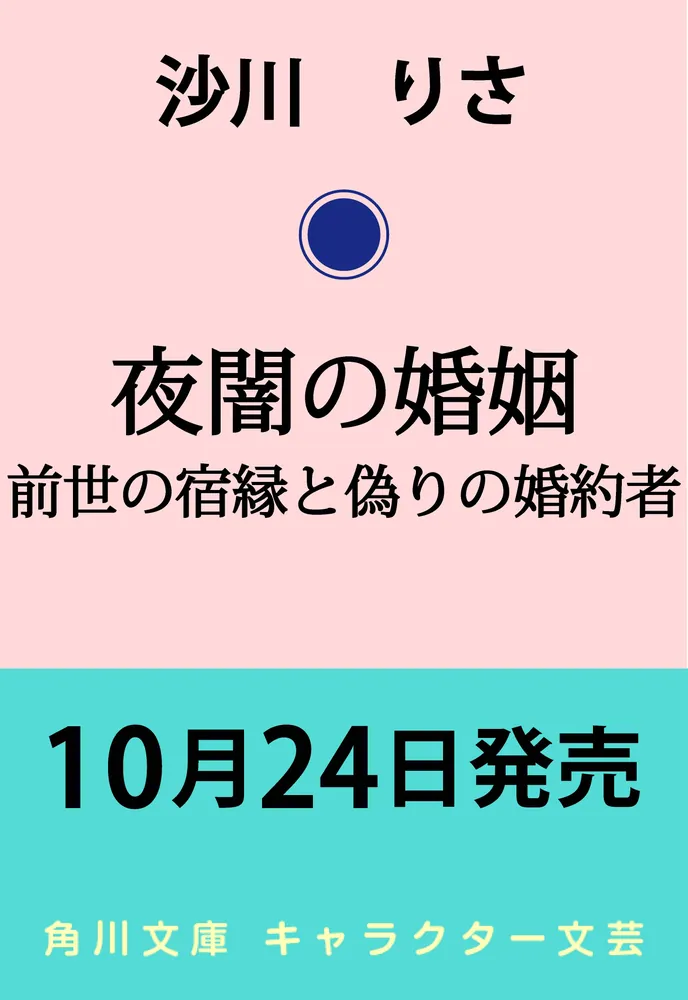
 書籍を購入
書籍を購入



応援すると応援コメントも書けます